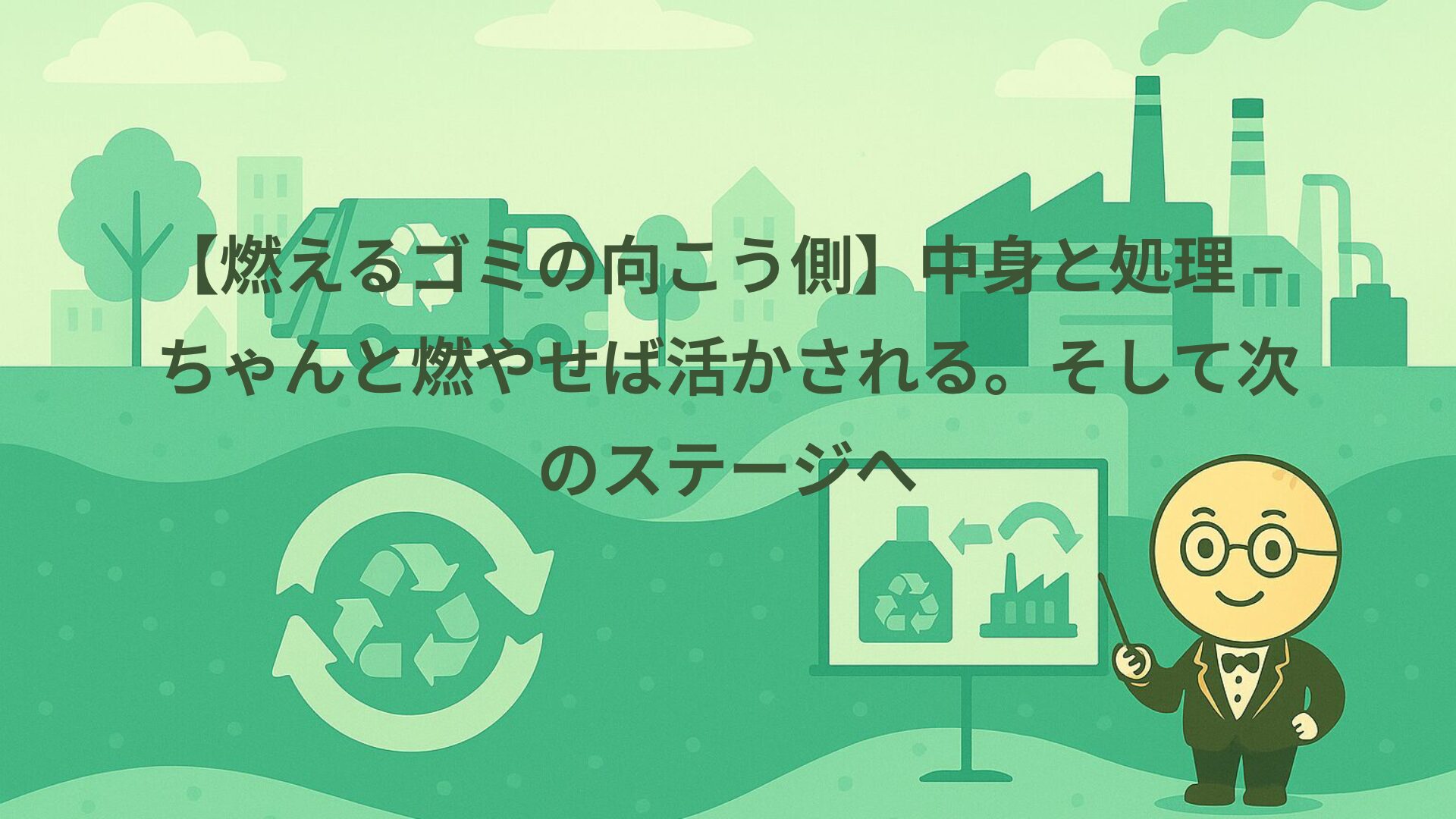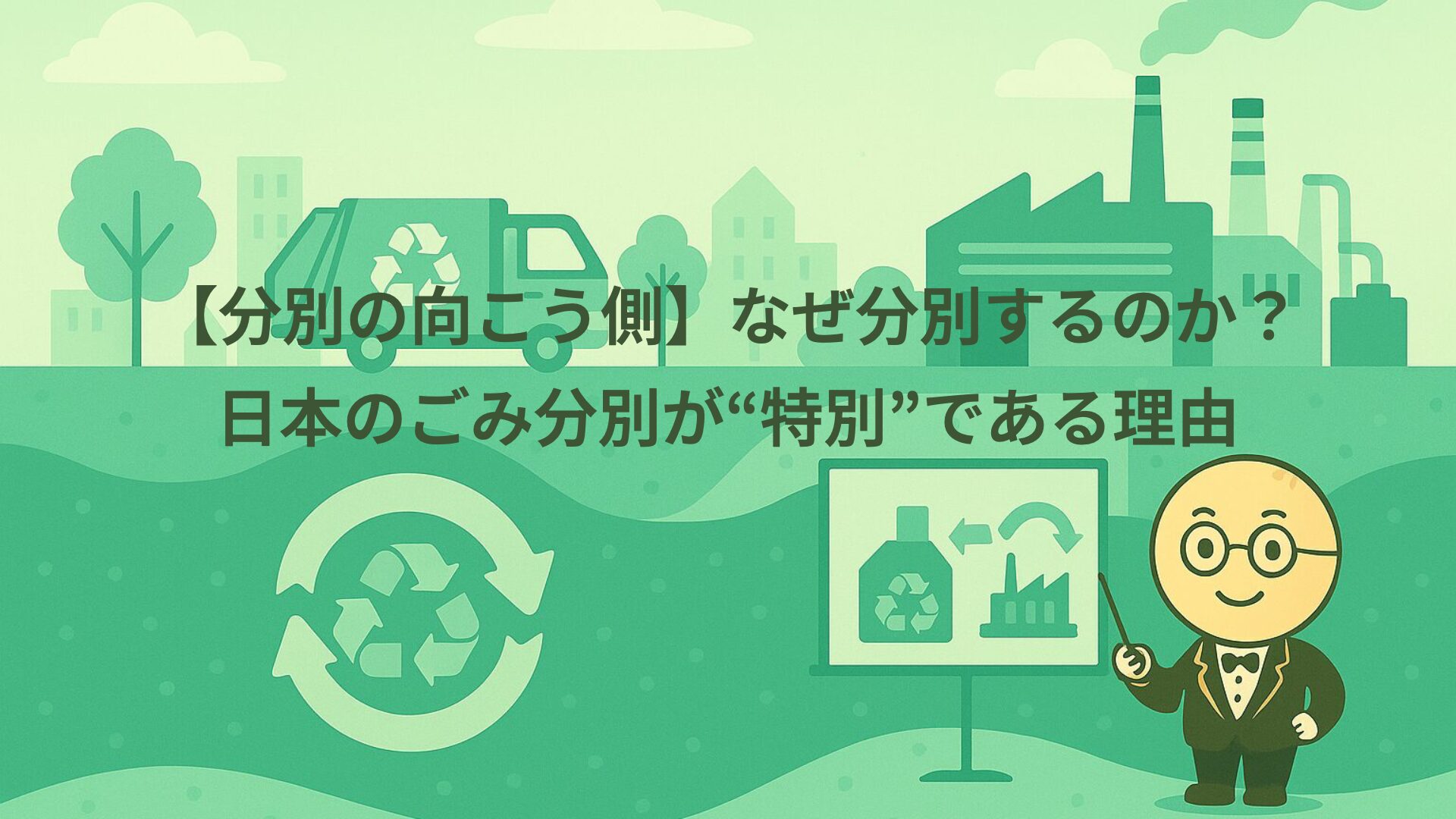【缶回収の向こう側】アルミもスチールも、どうやってリサイクル?

資源ごみの中でも「缶」は、分別しやすくリサイクル率も高い──そんな“優等生”と思われがちですが、本当にそうでしょうか?
- アルミとスチールは一緒でいいの?
- 飲料缶と缶詰、スプレー缶は同じ扱い?
- 洗って出さないとダメ?
- 自販機横のゴミ箱に入れた缶もリサイクルされてるの?
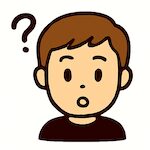
本記事では、そんな素朴な疑問に触れながら、家庭で分別された「缶」がどのように処理され、再び資源になるのかをたどっていきます。
アルミ缶とスチール缶、一緒に出していいの?
ジュースやビールを飲み終えて、空き缶を資源ごみに出す──
そんな時にふと、「これはアルミ?スチール?」「一緒でいいの?」と迷ったことはないでしょうか。
結論から言えば、多くの自治体では一緒に「缶」として出すことができます。
ですが、これは「混ぜてよい」という意味ではなく、回収後にしっかり選別する仕組みがあるからにほかなりません。
▽ 回収後に「磁力」で選別
- スチール缶(鉄製):磁石にくっつく
- アルミ缶:磁石にくっつかない
この性質を活かし、回収された缶は中間処理施設で磁力選別機により自動的に分類されます。
“一緒に出してOK”は、処理施設が分けてくれる前提です。
素材が混ざっているとリサイクル効率が下がることもあります。
缶にもいろいろ?飲料缶・缶詰・スプレー缶
「缶=資源ごみ」と思いがちですが、よく考えると缶にもさまざまな種類があります。
| 種類 | 主な用途 | 素材 | 一般的な分別例 |
|---|---|---|---|
| 飲料缶 | ジュース・ビール等 | アルミ or スチール | 資源ごみ(缶) |
| 缶詰 | ツナ・コーン等 | 主にスチール | 資源ごみ(缶) |
| スプレー缶 | 殺虫剤・整髪料など | スチール or アルミ | 危険ごみ or 金属ごみ |
| カセットボンベ | ガス調理用 | スチール | 危険ごみ(穴あけ不要の場合も) |
見た目は同じ“缶”でも、中身や性質によって処理方法は大きく異なります。
特に注意すべきはスプレー缶やカセットボンベ。
ガスが残っていると収集車や処理施設で爆発事故を引き起こすおそれがあるため、自治体では「別回収」「穴あけ不要」など厳格なルールが設けられています。
飲み終わった飲料缶=資源ごみ、それ以外の“缶”は要注意!
混ぜるとリサイクルルートが台無しになります。


回収後の流れ|缶はこうしてリサイクルされる
収集から再製品化までの道のりを、工程順にざっと把握します。
全体像がわかると要点がつかみやすくなります。
家庭から出た缶が、どのようなステップを経て再び資源になるのか、流れをシンプルに追ってみましょう。
缶のリサイクルフロー
- 家庭から集めた缶を中間処理施設へ運ぶ。
- 袋ごとの搬入で中身残り・汚れが多いと後工程に影響。家庭で空にして軽くすすぐが効く。
- 袋を開け、粗い異物を除いてラインへ載せる。
- 吸い殻・食品残さ・ビニールはここで歩留まりを下げる主因。異物を入れないがベスト。
- 磁力でスチールを回収。
- スチール缶にアルミ蓋やラベルが残ると選別精度が低下。自治体ルールに従い付属物は可能な範囲で除去。
- 残りからアルミを回収。
- 湿り・油分は選別効率を落とす。家庭で乾かす一手間が効果的。
- 材質ごとにブロック状に固める。
- 乾いた・異物少ないベールほど評価が高く、高付加価値リサイクル(缶to缶等)に回りやすい。
- ベールを金属リサイクル業者・製錬所へ運ぶ。
- 受入側で品質検査。
- 異物が多いとダウングレードや受入不可のリスク。
- 溶かして精製し、缶/板材/鋼材などに再生。
- 材質純度が高いほどCO₂削減・省エネ効果が最大化。とくにアルミは缶to缶が進む。
家庭でできる“協力ポイント”
リサイクル工程で生まれる誤差を最小化するために、家庭側で“協力できるポイント”具体策を3点に絞って押さえます。
処理工程のどこに影響が及ぶかを知ると、家庭での小さな工夫が意味を持つことが見えてきます。
- 空にする・軽くすすぐ・乾かす
- 汚れ・含水を抑え、歩留まりとベール品質が上がる
- 異物を入れない/吸い殻NG
- 選別精度と安全性を確保
- 自治体ルール順守(つぶす/つぶさない等)
- 設備仕様に合わせた効率化
アルミ缶とスチール缶、それぞれの行方
同じ金属でも、再生の行き先と価値の出方は違います。
アルミは「缶→缶」のクローズドループが主流、スチールは需要の裾野が広いオープンループ(建材・部品など)が中心。
なぜそうなるのかを、工程(製錬)・エネルギー・需要構造の観点でつかみます。
アルミとスチール、それぞれのリサイクル工程には特徴があります。違いを知ることで、なぜ分ける意味があるのかが見えてきます。
● アルミ缶は「缶 to 缶」の代表選手
- 洗浄・溶解・再製錬の工程を経て、またアルミ缶として再生
- 製造時のエネルギー消費を97%削減できるとされ、CO₂削減効果も高い
- 約3か月以内に再び飲料缶として店頭に並ぶケースも
● スチール缶は建材などにも活用
- アルミと同じく溶解・再製錬され、再び缶になることもある
- ただし多くは鉄筋・鋼材・自動車部品など別の用途に生まれ変わる
- アルミ缶リサイクル率:約97.9%(2023年・アルミ缶リサイクル協会)
- スチール缶リサイクル率:約91.0%(日本製缶協会)
数字を見てもわかるように、缶リサイクルは世界的に見てもトップクラス。
9割を超える回収・再生率は、ごみ分別の中でも“成功例”とされています。
現場のリアル|分別してもリサイクルできない例
リサイクル率の高い“優等生”素材といっても、適切に出されていなければ再資源化されないこともあります。
よくあるNG例
- 中身が入ったままの缶(飲料・油など)
- 食品の油分や汚れが落ちていない
- スチール缶にアルミの蓋がついたまま
- 異物が入ったまま(吸い殻、ゴミ、虫…)
こうしたものは選別工程で除外されたり、処理工程を妨げたりする原因になります。
“洗って、乾かして”はリサイクルの基本マナー。
缶は資源だけど、そのままじゃ資源にならないこともあるんです。
自販機横のゴミ箱や混合回収はどうなの?
家庭回収との違いが誤解されがちなポイントです。結論は「ルート次第」。
代表的な3パターンで実態を整理します。
1) メーカー・業界団体ルート(自販機横の専用回収)
- 飲料メーカーや業界団体が専用ボックスを自社回収→選別→リサイクル。
- 異物混入が抑えられ、高い再資源化率を維持しやすい。
- 家庭回収に劣らない品質確保が可能。
2) 事業系の「混合回収」(店舗ごみと一緒に回収)
- コンビニ・店舗で瓶・缶・PETを一袋で回収するなど、事業系一般廃棄物として処理。
- 異物や汚れが増えやすく、手選別負荷↑ → 歩留まり低下の懸念。
- 地域・事業者の運用により品質差が大きい。
3) 自治体収集と混在するケース
- 地域によっては店舗ボックスの中身が自治体ルートに合流する運用も。
- 分別状態が悪いと、一部が焼却側に回るリスクはあり得る。
店頭ボックスを使うなら、“缶だけ・液体なし”を徹底。
混ぜ物や中身残りは、その場の回収品質を一気に落とします。
まとめ|一手間かけて“ちゃんと資源”に
缶は、きれいに出されれば高い確率で資源に戻る優等生です。
アルミは缶to缶、スチールは用途の裾野が広く、いずれも純度が結果を左右します。
確実に循環へつなぐなら、家庭の資源回収に“空にして・すすいで・乾かす”——それだけで十分に効果的です。
sutekatainfo.comでは、家庭で迷いがちな“捨てかた”を入口に、ルールや背景・意味を紐解き、納得感を持って行動できる情報をお届けしていきます。
関連記事