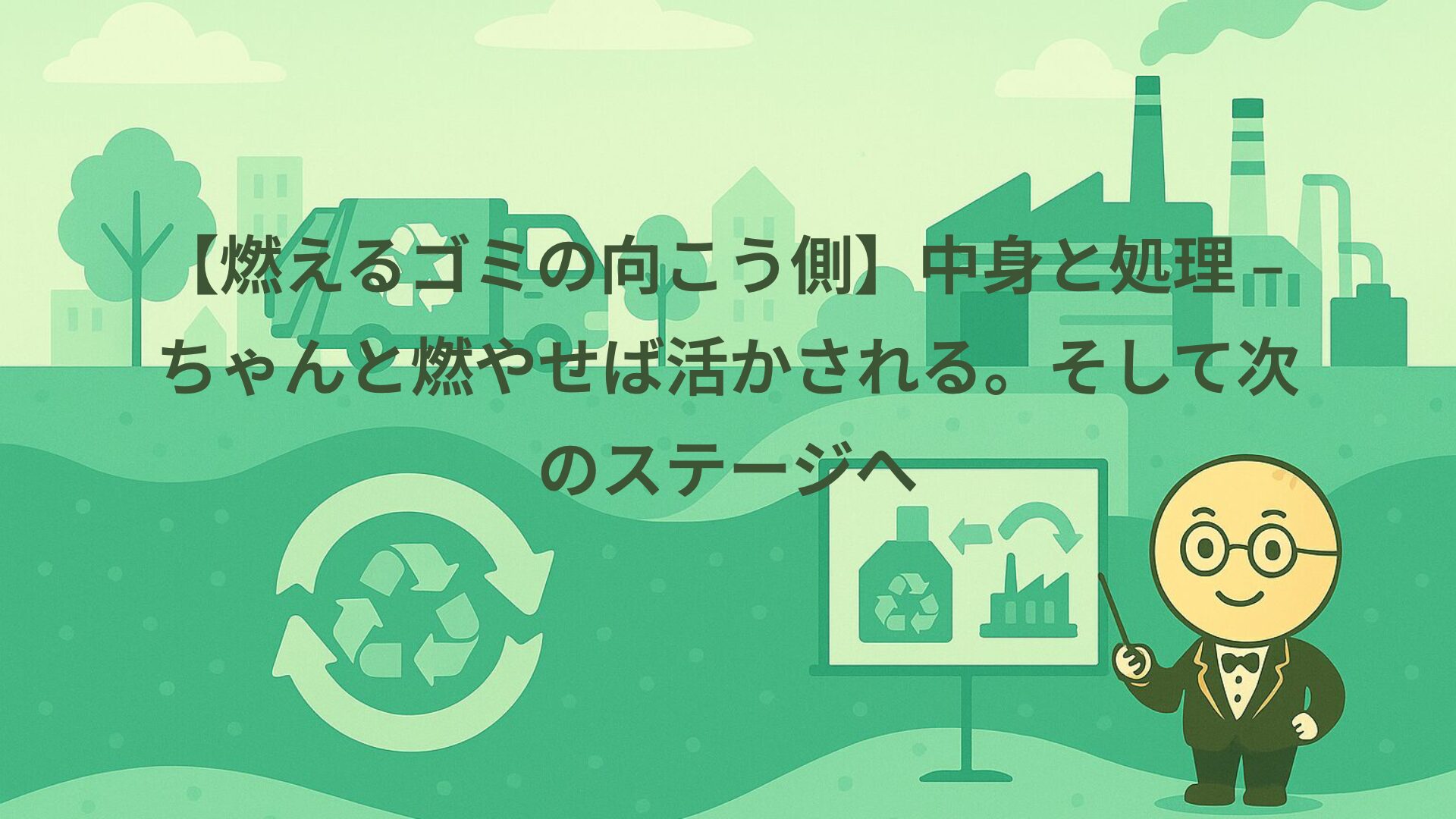【新プラ法の向こう側】製品プラと容リプラ、その違いと混合回収の現実

― メーカーの高品質リサイクルと自治体回収の現実 ―
毎日の暮らしで手にするプラスチック。
レジ袋やヨーグルトカップなど「容器包装プラスチック」については、すでに分別やリサイクルの仕組みが整えられてきました。
一方で、ハンガーや洗面器、バケツといった「製品プラスチック」はこれまで十分に扱われず、多くが燃やすしかありませんでした。
この課題に応えるために登場したのが、2022年施行の「プラスチック資源循環促進法(新プラ法)」です。
この記事では、その仕組みと現場の実態、そして「分ける意味があるのか?」という疑問に向き合ってみます。
なぜ「新しいプラスチックの法律」が必要だったのか
これまで日本のプラスチックごみは、「容器包装リサイクル法」に基づいて、ペットボトルや食品トレイなどと合わせて容器包装プラスチックが回収されてきました。
包装プラスチックの処理フローについては、すでに別記事で解説しています。

しかし、この仕組みではハンガーや洗面器、バケツなど、中身を入れる容器ではないプラスチック製品(製品プラ)は対象外。
多くが燃えるごみとして焼却に回っていたのです。
こうした背景から、資源の有効活用やCO₂削減を進めるため、2022年に施行されたのが「プラスチック資源循環促進法(新プラ法)」です。
新プラ法の概要
この法律は、メーカー側の責務強化と自治体への回収推進要請を二本柱にしています。
- メーカー(製造・販売事業者)
- 設計段階からリサイクルしやすい構造・素材にする義務(設計指針)
- 再生材利用や自主回収の努力義務
- 特定業種では自主回収計画の公表が求められる
- 自治体
- 製品プラを含むプラスチック資源の回収・リサイクルを推進する努力義務
- 回収方法や分別区分は地域裁量(分別回収/混合回収)
新プラ法の主役は“メーカーと自治体”。
ですが、市民も“分けて出す”ことで、その仕組みを動かす大切なピースになります。
容リプラと製品プラの違い
ここで改めて、容リプラと製品プラの違いについてみていきましょう。
容器包装プラ:
- 食品や商品を入れるための容器・包装。
- 比較的きれいで単一素材が多く、高品質リサイクルに向く。
- たとえばヨーグルトカップや食品トレイ、ペットボトルなどは、比較的均質でリサイクルしやすい素材が多いのが特徴。
製品プラ:
- バケツ、ハンガー、おもちゃなど容器以外のプラスチック製品。
- 汚れや複合素材が多く、リサイクル工程が複雑になりがち。
- 複数の樹脂を組み合わせたものや金属部品が付属するものも多く、単純に溶かして再生できない場合あり。
この違いが、どこで・どのように回収し、どう再資源化できるかに直結します。
容リプラは比較的効率よく資源化できますが、製品プラは技術やコストのハードルが高いのです。
同じ“プラスチック”でも、容リプラと製品プラでは性質も扱い方も別物。
まずはこの”違う”ということを知るだけでも大きな一歩です。
現場で進む「混合回収」
最近、地域によっては「プラスチックごみの分別ルールが変わった」方もいるかもしれません。
以前は容器包装プラだけ分けていたのに、今は製品プラも一緒に回収される──そんな自治体も出てきています。
新プラ法の理念では「容リプラと製品プラは別物」と整理され、高品質リサイクルのためにそれぞれの性質に合わせた扱いが求められています。
ところが現場に目を向けると、実際にはこの二つを一緒に集める“混合回収”が広がりつつあるのです。
制度設計と現場の運用の間にある、このギャップこそが大きな特徴といえます。
これは一部自治体で試験的に導入が始まっており、今後さらに広がる可能性があります。
背景には、社会全体の状況や技術の進歩が関係しています。
なぜ混合回収なのか
一見すると制度に逆行しているようにも見える混合回収ですが、導入が進むのにはいくつかの背景があります。
- 分別を細かくすると排出者の負担が増え、回収率が下がる懸念がある
- 中間処理施設での自動選別技術が進歩し、混合でもある程度仕分けが可能になってきた
- 人手不足や燃料高騰などで収集ルートを効率化したいという自治体の事情
- 国として「とにかく回収量を増やす」ことを優先したい意図もある
混合回収のメリットとデメリット
混合回収には効率面での利点もある一方で、リサイクル品質を損なう懸念もつきまといます。
その代表的なメリットとデメリットを整理すると、次のようになります。
メリット:
- 収集効率向上、住民の分別負担減、回収量の増加。
- 特に共働き世帯や高齢世帯にとっては分ける手間が減るメリットも大きい。
デメリット:
- 容リプラの品質低下、高品質リサイクルの割合が減る可能性。
- 製品プラに含まれる複合素材や汚れが混ざることで、結果的にサーマルリサイクル(焼却熱利用)に回される比率が高まるリスクもある。
こうしてみると、「制度上は分ける」「現場はまとめる」という一見矛盾した姿が浮かび上がります。
メーカーはリサイクルしやすい設計を進めていますが、混合回収で容リプラの質が下がれば、その努力が十分に活かされません。
読者の中にも「別物と言いながら結局まとめるの?」と疑問を抱く方がいるでしょう。
まさにこのズレが、新プラ法の実効性を左右する課題なのです。
制度と現場の間にある“矛盾”に気づくと、なぜ自分の地域がこの方式を採っているのか、見方が変わってきます。

矛盾が生まれる理由
メーカーは再生材の利用拡大や自主回収で質の高い原料確保を目指しています。
たとえば家電量販店やスーパーで設置されている回収ボックスは、メーカー直結の自主回収スキームの一例です。
これらは比較的きれいで選別しやすい製品が集まりやすく、高品質リサイクルにつながります。
一方で自治体の混合回収では質より量の確保が優先され、容リプラと製品プラが混ざることで原料の質が下がることも少なくありません。
せっかくメーカーが努力しても、自治体ルートで品質が下がれば十分に活かせないというジレンマが生まれます。
結果として、「メーカーの努力」と「現場の運用」が必ずしも噛み合わないという矛盾が生じているのも事実です。
“効率重視”と“品質重視”、両立が難しいからこそ制度と技術の工夫が求められています。

暮らしの中でできること
では、私たち一人ひとりの暮らしの中ではどのような工夫ができるのでしょうか。
大きな制度の動きと同時に、日常の選択も確実に循環の質を左右します。
- 自治体ルールを確認し、可能な限り分ける
- 店頭回収やメーカー直結ルートも活用(家電量販店、ホームセンター等)
- 購入時に再生プラ使用製品や長く使える製品を選ぶ
店頭回収ボックスは、自治体回収よりも“きれいで質の高いプラ”が集まりやすい仕組みです。
暮らしの中でこうしたルートを選ぶことが、メーカーの努力を後押しし、高品質リサイクルにつながります。



そもそも分ける意味あるの?に対する回答
短期的な処理コストだけを見れば、「まとめて燃やしたほうが効率的」という場合もあります。
焼却すれば発電や熱利用もできますし、処理フローはシンプルです。
しかし、長期的な視点では分ける意義は大きいです。
- 資源の確保:
- 石油由来のプラスチックを再生利用できれば、将来の資源リスクを減らせる
- CO₂削減:
- 燃やすよりも温室効果ガス排出を抑えられる可能性が高い
- 国際競争力:
- EUやアジアでは再生材使用率を求める動きが進み日本企業も対応が不可欠
“燃やした方が早いじゃん”は半分正しいけど、それは今だけの話。
10年先、資源や環境コストは必ず返ってくるので、今の分別はそのための投資なのです。

まとめ
新プラ法は、プラスチック資源の循環を加速させる重要な一歩ですが、その実現には質と量のバランスをどう取るかが課題です。
市民・自治体・メーカーがそれぞれの立場で工夫し、リサイクルの質を落とさずに循環の輪を広げることが求められます。
関連記事