【雑草/落ち葉の捨てかた】燃えるごみだが野焼きはNG!バイオマス資源として活用を

自然豊かな田舎で生まれ育った私にとって、雑草を取ったり、木の枝を切ったりすることは子供の頃から割のいいお手伝いで、夏の暑い日にも必死で作業をしていた記憶があります。
お小遣いをもらうことが一番の目的ではありましたが、当時はもう一つ楽しみがありました。
それは、家の裏の畑で、刈り取った雑草を燃やすことです。子供心に火遊びは特別な楽しみでした。
しかし、ある時から、環境への影響や地域社会への配慮からか、庭で燃やすことはできなくなりました。
今回の記事では、今では庭で燃やすことのできなくなった雑草の捨てかたについて解説します。
ルールを守ることは大前提として、雑草をゴミとして捨てるだけではなく資源として有効に活用する方法についても考えてみたいと思います。
雑草/落ち葉の捨てかた
もはや勝手に燃やすことができなくなった雑草の捨てかたについて、どうやって捨てれば良いかというルールに加えて、雑草を有効に活用する方法についても解説します。
可燃ゴミとして捨てる

多くの自治体では雑草は可燃ごみとして分類され、指定された収集日に出すことができます。
家庭で草を刈ったり、木を切った場合は、指定のゴミ袋に入る大きさ、容量に分けて、袋の口を硬く縛って燃えるゴミに出しましょう。
ここでポイントとなるのが次の3点です。
- 雑草の根についた土は払う
- 天日干しで乾燥させて体積と重量を減らす
- 袋に入れすぎない
やっぱり「燃やす」ことには変わりないんですが、庭で燃やすと近隣への煙や匂いの影響もあるしダイオキシンなんかの問題もあります。
焼却施設ででちゃんと燃やすというのが大切です。
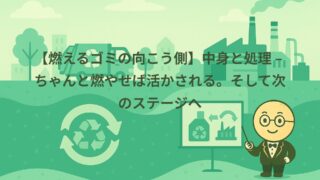
クリーンセンターへの個人持ち込み

ちょっと草むしり程度なら良いのですが、庭木の剪定や伐採など、大量の枝葉や雑草が出る場合は、全部小分けにして袋に入れることは難しいでしょう。
そんな時、一部の自治体(施設)では家庭から出る雑草をクリーンセンターに直接持ち込むこともできます。
軽トラやワゴンの荷台に乗せて運び込み、プラットホームで下ろすだけで一度に大量のゴミを処分できます。
無料のところや重量に応じて数十円から数百円程度の料金が発生するところなど、システムが異なりますので、お住まいの地域のクリーンセンターについて調べてみてください。

草木の持ち込みができる堆肥化施設
鹿児島県の大崎町や愛媛県の松前町、東京都の町田市などでは、せん定枝や刈り草の個人搬入を受け入れて堆肥化を行っている施設があります。
町内の家庭や事業所から出るせん定枝を受け入れてそれを堆肥化し、農業や園芸用の堆肥として販売したり、住民へ還元してくれます。
草木が燃えるゴミとして捨てるだけではなく堆肥化することで、堆肥として地域の中で有効に活用され循環する、物質もお金も回る循環型社会、サステナブルな社会に貢献できます。
他にも、ざっと調べたところいくつも対象の施設がありましたので参考にしてください。
- 千葉市:
- 剪定枝や刈り草を資源収集し、再資源化事業を実施しています
- 東埼玉資源環境組合:
- せん定枝や刈り草の個人搬入を受け入れ、堆肥の販売も行っています
- 流山市:
- 剪定枝などのリサイクルを行い落葉や雑草を袋に入れて持ち込むことができます
- 西東京市:
- せん定枝や落ち葉、草を分別収集し、堆肥化しています
大量の場合は専門業者に依頼するのも手
大量の雑草やせん定枝が出た場合は、専門の業者に引き取ってもらうというのも手です。
燃えるゴミとして出す場合や自分で持ち込むのに比べると、数千円から数万円程度の費用は発生しますが、最も簡単に処分する方法ではないでしょうか。
- 不用品回収業者:
- トラック1台あたり1から2万程度の費用が発生する
- 剪定から業者に頼む場合と費用はそれほど変わらないことがあります。
- 造園業者やガーデニング業者:
- 庭木の剪定枝などの回収・処分を日常的に行っており、依頼すれば処分のみでも受け付けてくれる場合がある
- 適切な方法で処理してくれる場合が多い
- 庭の手入れから全て依頼することもできる

雑草=バイオマス:資源として活用する方法
雑草や枝葉というとただのゴミとしてしか見れないですが、バイオマスと言い換えるとどうでしょうか。
途端に、資源という印象が持てるようになりませんか?
雑草も私たちの生活や環境に役立つ資源として活用することは、持続可能な社会を築く上で非常に重要です。
ここでは、雑草を有効に活用するいくつかの具体的な方法とその手順をご紹介します。
堆肥としての再利用:自然循環を促進する

雑草は、適切に処理されれば栄養豊富な堆肥に変わります。
コンポストと言われる方法で、微生物の力によってバイオマスを分解して、土・肥料に戻すというやり方です。
この自然由来のリサイクルプロセスによって、不要な雑草を使って土壌の質を向上させ植物の成長を促進させることができます。
具体的な手順や方法は別記事でまとめたいと思いますが、ざっくり手順はこんな感じです。
- 雑草を小さく切る
- これによって分解が速くなる。
- 乾燥させた雑草を堆肥化容器に入れ、土を被せる
- 容器は市販のものまたはDIYでもOK
- キッチンから出る生ごみなどと一緒に混ぜ、発酵を促進する
- 生ゴミを入れると、適度に水分が供給されて良いらしい
- 定期的にかき混ぜて、空気を供給しましょう
- 週に1回程度かき混ぜて分解促進。匂いや虫の予防にもなる
- 数ヶ月で堆肥が完成!

ガーデニングでの活用:雑草が美しい庭作りの助けに

実は雑草はガーデニングにおいても有用です。
乾燥させた雑草をマルチング材として利用することで、土壌の水分を保持し、雑草の成長を抑制することができるそうです。
下記が手順です。簡単ですね。
- 雑草を乾燥させる
- 雑草をとってすぐだと、また根を張る可能性があります
- 花壇や植物の周りに敷き詰める
- 全体に敷くほど量がない場合は茎の周りにだけでも良いそうです
- 土壌の水分蒸発を防ぎ、雑草の成長を抑える
- 光をさえぎることで雑草が生えにくくなるそう。
- 黒いシートと役割は同じです。
注意!やってはいけない処分方法
雑草の処分には、環境や他人に迷惑をかけないよう、避けるべき方法がいくつかあります。
ここでは、特に注意が必要な処分方法2つについて、その理由と、違反した場合の処分可能性について解説します。
無許可での焼却

2001年以降、日本では「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、無許可での焼却が原則禁止されています。
この法律は、ダイオキシン類などの有害物質の排出を抑制し環境汚染を防ぐために制定されました。
無許可で焼却を行った場合、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処される可能性があります。
例外として、農業経営者が業務に必要な範囲内で刈った草を燃やすことなどが挙げられますが、一般の家庭での雑草の焼却は、近隣への煙や臭いの迷惑、火災の危険性、環境汚染などの理由から禁止されています。
どうしても自宅で雑草を燃やしたいという場合には、お住まいの地域の条例や規制を確認し、自治体にも相談することをお勧めします。
火遊びをする機会が無くなったことは非常に残念ですが、法令で禁止されているので仕方がありません。
垣根の曲がり角で落ち葉焚きできない世の中になった代わりにSNSの炎上はよく見かけるようになりましたが。。。
燃焼は科学ですし、子供の頃に自然現象への興味や火の怖さを知ることも重要なのだと思う思います。
例外的にキャンプ場での焚き火などは認められていますので、子供達にそういう機会を提供してあげることが大切だと改めて感じました。
不適切な場所への不法投棄
不法投棄は、土壌汚染や水質汚濁などの環境問題を引き起こすだけでなく、人体への健康被害にも繋がる恐れがあります。
土に還るのだからと安易に雑草を捨てる行為は、実際には土壌の質を損ない、生態系に悪影響を及ぼすことがあります。
不法投棄された場所の原状回復には多くの時間と費用がかかり、社会的な問題となっています。
当然のことながら不法投棄は法律で禁止されており、個人が不法投棄をした場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方の刑に処されます。
先手必勝!雑草を減らすための予防策
雑草の捨てかたを考える前に、雑草が増えるのを防ぐという先回り的な発想があります。
雑草の発生を事前に防ぐことは、手間を省くと同時に環境にもやさしい一石二鳥なのです。
ここでは、雑草の効果的な予防策として、防草シートの使用と除草剤の適切な使用方法をご紹介します。
防草シートを使用する
防草シートは、雑草の成長を物理的に阻止するための簡単で効果的な方法です。
このシートは、土壌と直接接触することで雑草の光合成を妨げ成長を抑制します。
比較的安価でそれなりの効果が見込めるため、庭先全体をカバーするといったやり方で雑草が生えるのを防ぐことができます。
- 土壌を平らにし、石や根などの障害物を取り除く。
- 事前に雑草は取っておく。
- 防草シートを敷き詰め、専用のピンやアンカーで地面に固定する
- シートの上にマルチや砂利を敷くことで、見た目を整えるとともに、シートの固定を強化する
メンテナンスを怠ると、上の「注意点」でも記したとおり、無理やり環境改変をしようとした挙句に、かえって土壌汚染や環境悪化につながっていると見えてしまいます。
田舎だと、高齢で手入れできなくなった庭でこういったシートと土がまだらになっているお家とかも見かけます。
あくまで、都会の住宅の庭先での使用に向いていると思います。
除草剤を使用する
最も手っ取り早く雑草をなくす方法は、除草剤を撒いてしまうことかもしれません。
ただ強力な除草剤を撒きましょう、だと本サイトの趣旨から逸れるので、ここでは環境に配慮しながら効果的な除草剤の使用方法をご紹介します。
環境に優しい除草剤の選び方
- 農林水産省による農薬登録がされているもの
- 安全性と環境負荷への配慮の証明として農林水産省の農薬登録を選ぶ
- ラベルに「農林水産省登録第○○○○号」と記載されているものを選ぶ
- 植物由来の成分で作られているもの
- トウモロコシやお茶、柑橘類に含まれるペラルゴン酸は、植物の細胞を破壊する性質を持ち除草効果を発揮する
- 土壌中で生物分解されるため、使用後も環境負荷が少ない
- 除草成分に食酢が使われているもの
- 食酢を除草成分として使用している除草剤もある
- 食品成分なので、使用後の環境への影響が少ない
効果的な使い方と注意点
- 散布する際は、風向きや周囲の環境に注意
- 他の植物や水源に影響を与えないように配慮しましょう
- 適切な時期と天候で使用
- 雑草が生える前、晴れた日に使用すると効果が高まります
- 子供やペットが触れ(食べ)ないように注意
- 散布後は安全が確認されるまで接触させない
まとめ
この記事を通じて、雑草や剪定枝の捨て方から予防策まで環境に配慮した選択肢を紹介しました。
「雑草/剪定枝=バイオマス」そう考えると、捨てかたにも色々な選択肢が見えてくるのではないでしょうか。
刈り取った草・枝葉を見て、自分の庭で作られた大事な資源をどう活用するか、そんな風に考えられると、自然との向き合いかたも変わってくると思います。
この記事が、雑草・枝葉との良い付き合いかたを見つけるお手伝いになれば幸いです。







sutekatainfo.comでは、家庭で迷いがちな“捨てかた”を入口に、ルールや背景・意味を紐解き、納得感を持って行動できる情報をお届けしていきます。






