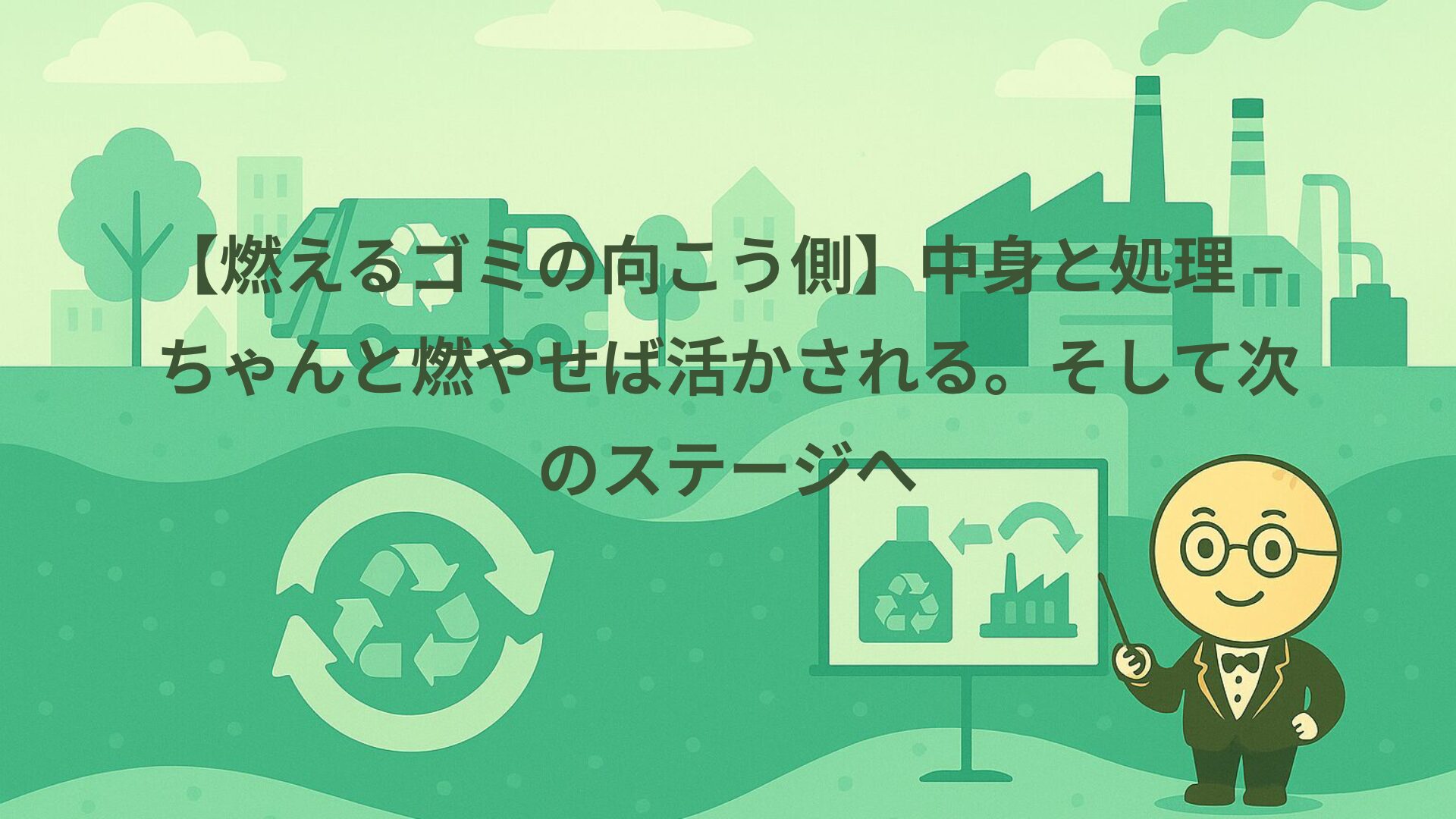【金属ゴミの向こう側】分ければ資源、混ざればトラブルのもと

毎日の暮らしでよく見る、鍋・フライパン、金属ハンガー、トング。
つい“不燃ゴミ”と考えがちですが、多くの自治体ではこれらを金属ゴミとして別回収しています。
本記事は、捨てたあとに起きていること――収集→選別→溶解→再製品化という“向こう側”の工程を、制度の背景とあわせて解説します。
基本的に金属は焼却できません。
だからこそ資源として取り出す前提で設計された流れになっています。
金属ゴミという区分(本記事での立ち位置)
本記事は工程と背景に焦点を当てます(How toはそれぞれの「捨てかた記事」に委ねます)。
金属ゴミの定義(本記事での整理)
本記事は工程理解のための“一般的な定義”を示します。
実際の出し方は自治体ルールに従ってください。
対象の範囲
- 家庭から出る小型の金属製品(目安:一辺30cm未満/自治体差あり)
- 主たる構成材が金属であるもの(プラ部材が付いていても“金属主体”なら含まれることがある)
含まれることが多い例
- 鍋・やかん・フライパン(取手が金属のもの)
- 金属ハンガー、トング・お玉・トレー、ペンチ・スパナなどの小型工具
- 傘の骨・物干し金具などの小型パーツ



別ルートになるもの(工程が異なる)
- 小型家電(電池・コード・基板を含む)→ 小型家電リサイクル
- 粗大ごみ(大型の金属家具・長尺物)→ 破砕・粗大系ライン
- スプレー缶/カセットボンベ → 危険物・資源缶ルート




自治体差が大きい境界例
プラ柄付き包丁・傘・フッ素加工フライパン・複合素材品 などは自治体によって判断が異なることもあります。
多くは“金属主体”かどうかで扱いが分かれますが、区分は自治体基準が最優先。
ここでの定義は向こう側(処理工程)を理解するための整理です。
家庭での分別HowToは「捨てかた記事」で詳しく扱います。
背景と構造(なぜ金属だけ別ルート?)
金属を“別ルート”にしているのは、素材特性(燃えない・劣化しにくい)と経済性(価値が戻る)に根ざした設計です。
一般ごみの焼却・埋立ラインに混入すると、安全・品質・コストのいずれも悪化します。
だからこそ、最初から「取り出して活かす」前提で流れを組む——その考え方を3点で押さえます。
- 焼却・埋立に不適:
- 金属は燃えず、埋めても劣化しにくい。
- 「燃やす/埋める」主流工程から外し、回収・資源化を前提にルート設計。
- 価値が戻る素材:
- 金属は繰り返し再生可能。
- 素材価値の回収が処理費の一部オフセットにもつながる。
- 都市鉱山の視点:
- 生活ごみ中に散在する金属は“埋もれた資源”。
- 集めて品位を上げることが、国内資源の底力を支えます。


金属ゴミの処理の流れ
- 自治体の指定日に回収。金属は他の不燃とは別ルートで中間処理施設へ。
- 回収時点での“混ぜない設計”が、その先の効率と安全性を左右します。
- 磁選機(マグネット)
- 鉄(スチール)を吸着・回収
- 渦電流分離装置
- アルミを電磁力で跳ね分けて回収
- 手選別・破砕・比重選別
- ステンレスなどを仕分け、異物を除去
- 素材ごとに圧縮・保管されたスクラップは、製鉄所・非鉄精錬・再生アルミなどへ出荷
- ここから先が“新しい命を吹き込む工程”です。
- 溶解
- 鉄は高炉・電気炉で1,500℃級、アルミ・銅は専用炉でより低温域。金属を液体状態にして均質化します。
- 精錬
- スラグとして不純物を分離し、必要な品位まで品質調整。
- 成形
- 鉄:厚板・棒鋼・H形鋼などの鋼材へ → 建築・土木・自動車部材
- アルミ:板・ビレット → 缶・家電筐体・機械部品
- ステンレス:鋼板・棒材 → 厨房器具・配管・医療器具
- 銅:銅地金・導体 → 電線・配管
「今日のフライパンが、数か月後には建物の骨や自転車の部品になる」。
これが金属の循環のダイナミクスです。

材質ごとの違い(工程・価値の“見どころ”)
同じ「金属」でも、磁性の有無や比重、耐食性の違いで選別機の設計も出口の価値も変わります。
ここでは家庭で目にする主要4材について、工程の“見どころ”と再生後の行き先をコンパクトに俯瞰します。
| 材質 | 工程上の特徴 | 価値・主な行き先 |
|---|---|---|
| 鉄(スチール) | 磁選で回収しやすい/量が多く安定 | 製鉄所の電炉材→建材・自動車骨格など |
| ステンレス | 磁性が弱く、手選別・比重選別の出番 | 厨房・医療・配管など耐食用途 |
| アルミ | 渦電流分離で回収/低温で再生しやすい | 缶・筐体・機械部品など軽量用途 |
| 銅 | 家電や配線由来/高価値 | 電線・配管などインフラ用途 |
どんな金属かによって、使う機械や手順も、その先に何になるか(建材・缶・電線など)も変わります。
現場では「集めやすさ」と「生まれ変わったときの価値」のバランスを取りながら仕分けしているのですね。
現場の実態と課題(“混ざる”コスト)
金属が本来とは異なるルート(可燃・容リプラ・古紙など)に混ざると、向こう側では次のようなリスクが一気に高まります。
各処理ラインは想定原料(可燃物・プラスチック・紙など)に合わせて設計されています。
そこへ金属が入ると、燃えない/硬い/導電するといった特性が、温度管理・選別精度・機械寿命に直接影響します。
結果として、コストと品質を同時に悪化させます。主なリスクは次のとおりです。
- 火災・爆発:
- 電池・スプレー缶・残ガス由来の発火
- 設備損傷・ライン停止:
- 投入装置・コンベア・破砕刃・火格子の損耗や噛み込み
- 品質低下・受入拒否:
- 他資源のベール品質劣化→単価下落や返品
- コスト増:
- 緊急清掃・修理・人件費、焼却残渣や選別残渣の増加
- 労働安全:
- 袋破れ・飛散・切創など現場負担の増大
金属は金属のルートへ。
これだけで、安全・品質・コストの“三方良し”が実現します。
まとめ|“捨てる”は終わりではなく、次の工程の始まり
金属ゴミは、分ければ資源、混ざればトラブル。
収集から選別、溶解・精錬・成形を経て、建材や部品として社会に戻ります。
分別の意味は、向こう側の工程が最大限に活きるように“質を揃える”こと。
その一手が、資源循環の背骨になります。
次に金属を出すときは、出口(磁選・渦電流・溶解)を一瞬だけ思い浮かべてください。
あなたの一手が、向こう側での安全と歩留まりを確かに高めます。
sutekatainfo.comでは、家庭で迷いがちな“捨てかた”を入口に、ルールや背景・意味を紐解き、納得感を持って行動できる情報をお届けしていきます。
関連リンク