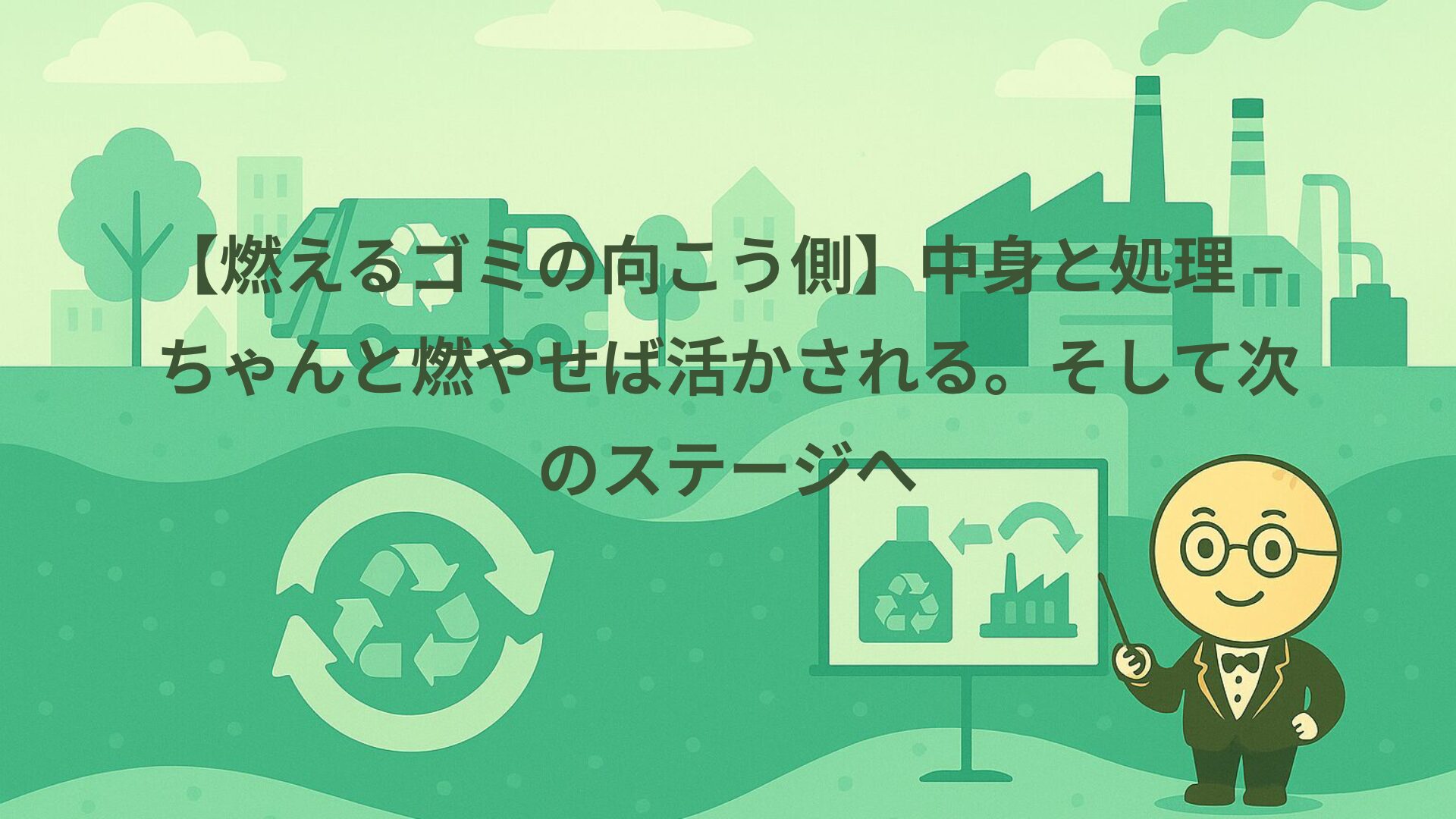【不燃ゴミの向こう側】埋め立てだけじゃない!処理の流れと分別の工夫

それ、本当に「不燃ゴミ」ですか?
燃えないんだから不燃ゴミでしょ?

そんなふうに、なんとなくで分別していませんか?
でも実は、不燃ゴミは処理コストが高く、環境負荷も大きい分別区分です。
しかも、その中には資源として回収できるものも多く含まれています。
この記事では、「不燃ゴミ」がどう扱われているのか、そしてなぜ減らす必要があるのかを、処理の流れとともに掘り下げてお届けします。
制度や区分の定義:不燃ゴミとは何か?
不燃ゴミ=分別できずに残ったごみ
一般的には、以下のような素材が不燃ゴミに分類されます:
- ガラス類・陶磁器類(皿、コップ、鏡など)
- 金属類(鍋、やかん、スプーン、工具など)
- ゴム製品・皮革製品(靴、ベルトなど)
- 硬質プラスチック(CDケース、ハンガーなど)
ただし、次のようなものは別扱いになることも多く、自治体ルールを要確認です:
- スプレー缶・ライター・電池類 →「危険ごみ」
- 小型家電 →「資源ごみ」または「リサイクル対象」
不燃ゴミは「燃えないもの」ではありますが、「埋め立てるしかないもの」ではありません。
素材や仕組みに注目するとより良い処理のヒントが見えてきます。


処理の流れ:不燃ゴミの処理は手間がかかる
「燃えないから不燃ごみ」「燃えないから埋めるしかない」――そう思っている人は少なくないでしょう。
でも実際には、不燃ゴミは破砕・選別という工程を経て、資源と廃棄物に振り分けられているのです。
一般的な処理フロー
- 地域のルールに従って集められ、処理施設へ運ばれます。
- 重くてかさばるため、燃えるゴミよりもコストが高い。

- ガラスや金属などを大型の破砕機で細かく砕きます。
- 磁力選別などで金属を取り出し、資源としてリサイクル。
- 燃やせない陶器やガラスの破片などは、最終処分場に埋め立て


現場の実態や課題:コストを左右するのは「分けられているか」
家庭で分別すれば、コストが減る
たとえば鍋や傘、使わなくなった小型家電など。
家庭で素材ごとに分けて出せば、破砕や選別の手間がぐんと減り、処理費用も抑えられます。
家庭でできるちょっとした工夫
- 傘は骨と布を分けて出す(骨は金属ごみ、布は燃えるごみ)
- CDプレーヤーなどの小型家電は、自治体の回収ボックスへ
- 鍋やフライパンは、資源ごみ扱いできる自治体が多数
破砕処理に頼らず、家庭で分けて出すだけで「再資源化の効率」が上がります。
最終処分の量も減らせて、いいことづくし!
行動変容につながる気づき:これは本当に「不燃ゴミ」?
「とりあえず不燃ゴミ」と思い込んでいるものの中には、分別次第で資源になるものがたくさんあります。
| よくある品目 | 分別のヒント |
|---|---|
| アルミ鍋・やかん | 金属ごみ(資源)として回収可 |
| 割れたガラス皿 | ガラス資源ごみに分類する自治体あり |
| デジカメ・スマホ | 小型家電回収ボックスへ |
| スプレー缶 | 穴あけ禁止。危険ごみとして別回収 |
| CD・DVD | プラごみ扱いの地域もあり |
こうした判断が1つひとつ積み重なれば、最終的に埋め立てられる量も、かかるコストも減らせます。



制度・仕組みの背景:「不燃ゴミ」の役割と限界
不燃ゴミという区分は、「焼却できないものを安全に処理する」目的で設けられています。
しかし現在は、
- 小型家電リサイクル法
- 容器包装リサイクル法
- 自治体独自の資源回収制度
などの整備が進んだことで、「不燃ゴミ」の範囲は徐々に小さくなってきています。
「とりあえず不燃」という発想は、制度設計の観点からも過去のもの。これからは、素材に応じて資源ルートを選ぶ時代です。



まとめ:「不燃ゴミ」は“なんでもOK”じゃない
不燃ゴミの多くは、埋め立て処分される前に選別工程を経ています。
でもその作業には、高額なコストと手間がかかっていることを、私たちはあまり意識していません。
家庭で分解・分別しておけば、
- リサイクル効率が上がる
- 埋め立て量が減る
- 税金(処理費)が抑えられる
という三方良しの結果につながります。
「とりあえず不燃」はもう卒業し分けられるものを、家庭で分ける。それだけで、未来のごみ処理の姿が変わります。
sutekatainfo.comでは、家庭で迷いがちな“捨てかた”を入口に、ルールや背景・意味を紐解き、納得感を持って行動できる情報をお届けしていきます。
関連記事