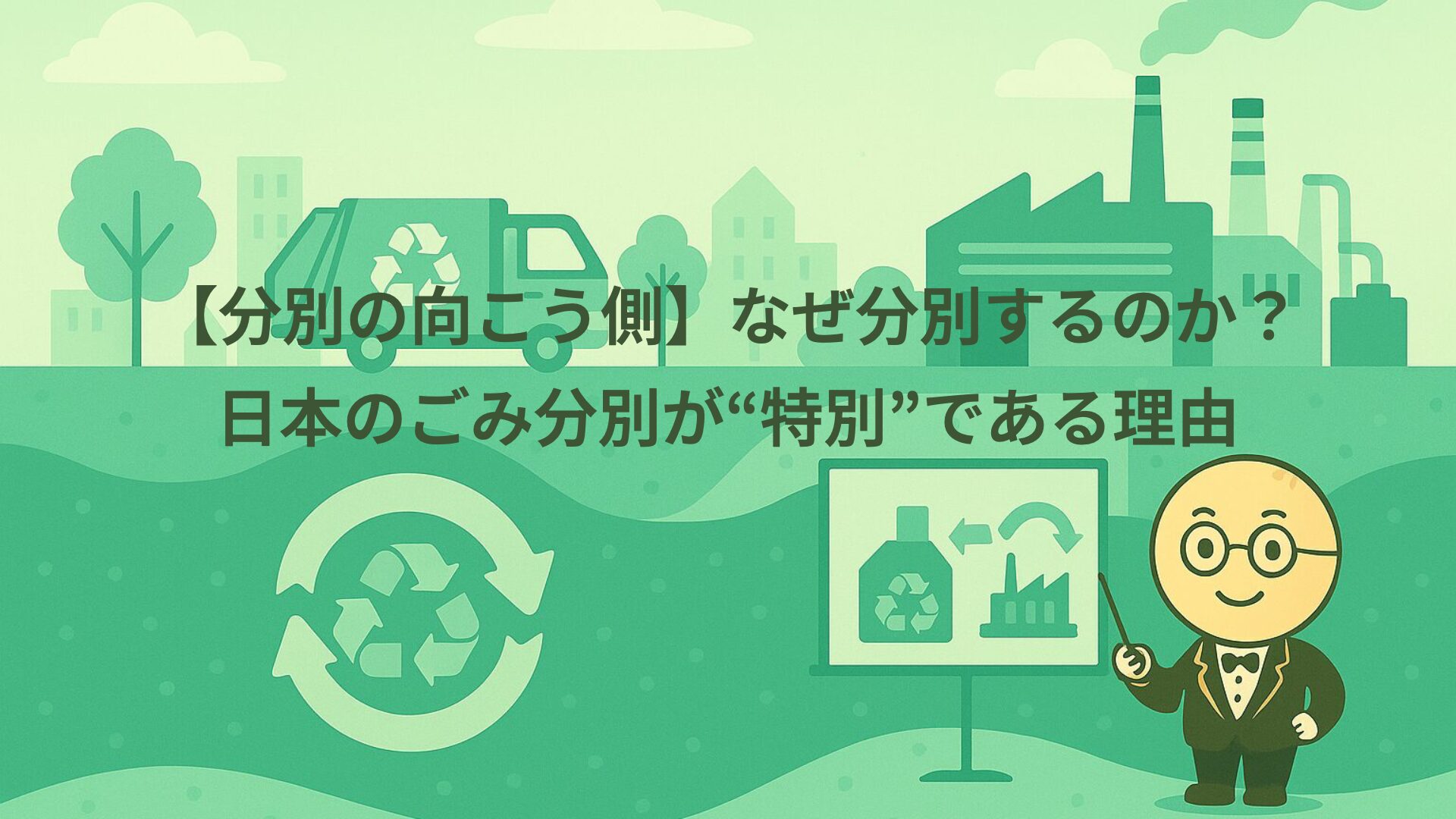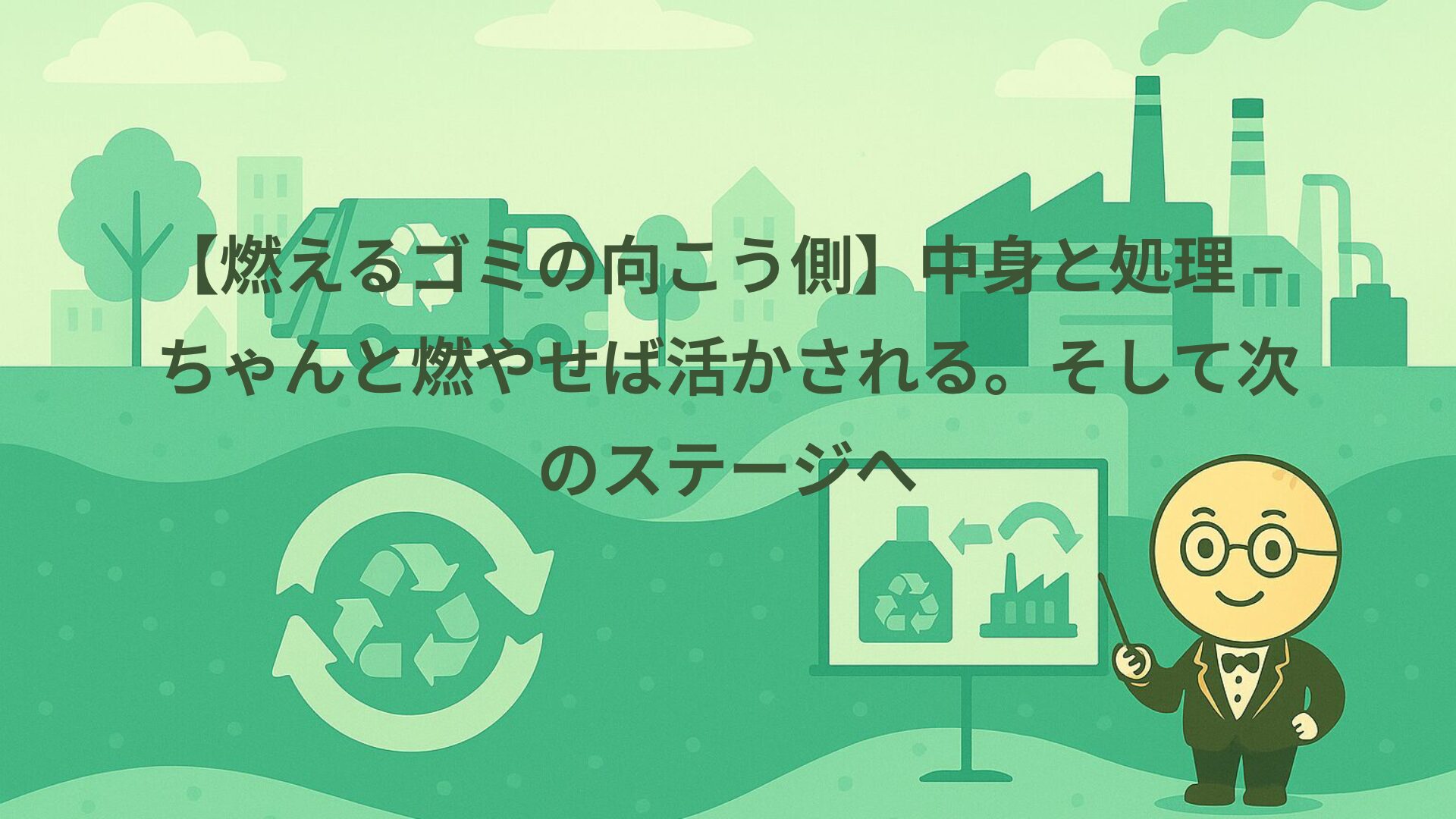【ペットボトル回収の向こう側】制度の舞台裏と、店頭回収で進むボトルtoボトル

ペットボトルは、私たちが日常的に手にするプラスチック容器の中でも、とくに「分別ルール」が細かい存在です。
ラベルをはがす、キャップを外す、軽くすすぐ——。
気づけば習慣になっている人も多いでしょうが、その理由や、出したあとどこへ行くのかまでは知らない人も多いはずです。
この記事では、分別ルールの背景から、回収後の行き先、そして制度と現場がどう支えているのかまでをたどります。
さらに近年広がる民間企業の自主回収にも触れ、「私たちが関われる次の一手」を探っていきます。
ペットボトルだけ“特別扱い”なのはなぜ?
ペットボトルは、全国的にほぼ例外なく「容器包装プラスチック(容リプラ)」とは別枠で回収されます。
これは見た目や素材の軽い違いではなく、制度とリサイクル技術の両面から必然性があることです。
- 素材(PET)が均質で、再資源化しやすい
- 用途が飲料に限られ、異物混入が少ない
- 「ボトルtoボトル」リサイクルが現実的に可能
背景には「資源有効利用促進法」や「容リ法」による再商品化義務があり、メーカーや再商品化事業者は、一定以上の品質で再資源化することを求められています。
そのため、家庭からの分別回収が制度上の大きな柱となっています。

分別ルールは“マナー”ではなく、工程の前提条件
ここで言う「外す・はがす・すすぐ」は、マナーではなく、後段の選別・洗浄・再生で要求される純度基準を満たすための工程要件です。
だれがどこで何を担保するのか——制度の分担と現場の制約という二つの視点で、次の要点を短く確認します。
- ラベル・キャップはPETと別素材(PP/PE)
- 一緒に溶かすと物性が落ち、ボトルtoボトルの歩留まりが下がる
- 汚れが残る=洗浄強化
- コスト増/品質ばらつき
- 再商品化事業者には品質基準や報告義務あり
- 家庭での分別精度がそのままコスト・品質に響く
だから、外す・はがす・すすぐは「現場が助かる気遣い」以上に、制度を成立させる前提条件でもあるわけです。
ゴミ箱の向こう側:回収後の旅路
分別されたペットボトルは、自治体や委託業者によって収集され、中間処理施設へ。
ここから先が、多くの人が見たことのない「向こう側」です。
- 自治体や委託業者によって収集され、中間処理施設へ。
- メーカが独自で回収する別ルートも。
- 大型のコンベア上で異物や汚れを目視確認。
- ラベルやキャップの残りも手作業で除去されます。
- かさばるボトルを圧縮して「ベール」と呼ばれる塊に。
- 海外輸出される場合もあります。
- 数センチ角に砕き、温水と洗剤でラベル糊や汚れを落とします。
- ここで混ざっていた異素材は比重選別や風力分離で除去。
- 洗浄後のPETを乾燥・溶融し、再生用の粒(ペレット)や薄片(フレーク)に加工。
- ボトルtoボトル、衣類用繊維、建材、自動車部品など、多様な製品へ生まれ変わります。
この流れのどこかで異物が混ざると、飲料ボトルへの再生は不可能になります。
だからこそ、家庭での分別が“入口の品質管理”として重要なのです。
数字で見る“いま”:量は確保、質を伸ばす段階へ
ここまで仕組みと現場の流れを確認しましたが、ここでは現状を数字で簡潔に整理します。
全体の量は着実に集められている一方で、どれだけボトルに戻せているかは、これから伸ばしていける部分です。
まずは現在地を3つの数値で押さえておきましょう。
- リサイクル率:85.0%(2023年度)
- 前年(2022年度)は86.9%。
- 有効利用率(※熱回収含む)は98.8%との推計。
- ボトルtoボトル比率
- 最新公表で29.0%(2022年度)。
- 伸びてはいるが、まだ伸びしろが大きい領域。
- 「リサイクル率」
- 主にマテリアルリサイクル(ボトルtoボトルや繊維等)
- 「有効利用率」
- 熱回収まで含む広い指標
見かけの数字が高くても、循環の質を評価するならボトルtoボトル比率がカギです。
制度だけでは届かない、高品質リサイクル
制度による家庭回収は広域に安定して資源を集められますが、品質のバラつきが課題です。
一方、近年は飲料メーカーや流通業が独自の回収ルートを持ち、品質を確保したうえで高効率な再資源化を進めています。
● サントリー(BtoBを軸にした水平リサイクル)
自治体ルートだけでは届きにくい純度とトレーサビリティを、自社回収とパートナー連携で補完するモデルです。
『狙って集める→品質担保→水平リサイクル』を短い動線で実現し、ボトルtoボトル比率を底上げします。
- 店頭やイベント会場に専用回収ボックスを設置
- 汚れや異物の少ない状態で回収し、自社ルートで100%リサイクルPETボトルに再生
- 植物由来PETや再生材との組み合わせで、石油由来原料ゼロを目指す
● セブン&アイ(店頭回収×ポイント還元)
生活動線の上に回収機を置き、インセンティブで参加を広げる小売主導のモデル。
店舗で集めたボトルを国内で再生→再び飲料ボトルへつなぐ、“店舗発のクローズドループ”です。
- 全国の店舗にペットボトル回収機を設置し、ポイント付与で利用を促進
- 回収品は国内で洗浄・再生され、再び飲料ボトルとして利用
- 年間1万トン以上の回収量(2022年度)
こうした民間ルートは、短い工程で高品質リサイクルを実現できる点が強みです。
民間ルートは短い工程×高い純度が武器。
“またボトルに戻す”確率を上げたいなら、店頭回収も選択肢です。
回収ルートの舞台裏と制度のアップデート
家庭の分別回収は基盤として大切です。
一方で、民間の事業系回収や制度の見直しによって、出し先や品質担保の方法が広がっています。
ここでは、現場の回収設計と制度のアップデートをあわせて整理します。
事業系回収:自販機横のごみ箱にそのまま捨ててOK?
家庭の資源回収と同じに見えますが、配線(ルート)が異なります。
ここは自治体ではなく設置者(飲料メーカー・小売・オペレーター等)が管理する事業系回収。
そのため、回収後の処理や再生先の設計を現場側で最適化できます。
- 流れ
- 箱→設置者の集荷→選別・圧縮(ベール化)→民間の再資源化へ
- 強み
- 動線が短く、異物が少ない設計にすれば高品質リサイクルに寄せやすい
- 課題
- 箱の設計・運用がまちまちだと品質保証やトレーサビリティにばらつきが出る
この課題を埋める解が店頭の専用回収機です。
投入口をPET専用に絞り、残液検知や圧縮、投入本数の計測まで機械側で“品質と記録”を担保。
結果としてボトルtoボトルに直結しやすい素材を安定的に集められます。
法制度の新潮流:プラ資源循環促進法(2022)
制度も“出し先の選択肢を増やす”方向へ舵を切りました。
2022年のプラスチック資源循環促進法は、製品の設計→流通→回収→再生までを一気通貫で捉え、自治体だけに頼らない循環を後押しします。
- 設計段階
- 単一素材化・ラベルの工夫・再生材の採用など、リサイクルしやすい設計を促進
- 回収段階
- 小売・外食・オフィス等の店頭回収・事業系回収を制度的に後押し
- 再生段階
- 国内での再商品化・水平リサイクルの拡大に向けた官民連携を想定
要するに、“どこで誰が純度を担保するか”の選択肢が広がったということ。
家庭で丁寧に出すことはこれまで通りの基盤ですが、そのうえで民間の回収機や専用ボックスを使うという選択が、質の面で効いてきます。

今日から選べる“協力パターン”
ここまで制度と回収ルートの全体像を見てきました。
ここからは、日常の動線で選べる協力のかたちを三つだけ。無理なく続けられるものから取り入れてみてください。
- A:いつもどおり自治体ルールで丁寧に
- 外す・はがす・すすぐ。
- 制度の土台を支える王道です。
- B:店頭の回収機を使う
- 買い物ついでに回収機へ。
- ポイント特典がある店舗も(例:nanaco連携)。
- ボトルtoボトルに直結しやすい選択。
- C:ボトルtoボトル製品を選ぶ
- ラベルやサイトで“100%リサイクルPET”の表示をチェック。
- 需要側の合図になります。
完璧でなくてOKです。
“向こう側”を知ると、自然と協力したくなったりしますよね。
そもそも水筒を使うというのも効果的です。

まとめ:向こう側を知ると、ひと手間の意味が変わる
ペットボトルは、制度の上で「資源」として扱われ、現場の手で品質を守られています。
家庭での分別も、民間ルートでの回収も、それぞれがリサイクルの歯車を回す役割を担っています。
ゴミ箱に入れた瞬間に終わるのではなく、その先でどんな工程が待っているのか。
向こう側を知れば、ひと手間の意味がはっきり見えてくるはずです。
sutekatainfo.comでは、家庭で迷いがちな“捨てかた”を入口に、ルールや背景・意味を紐解き、納得感を持って行動できる情報をお届けしていきます。
関連記事