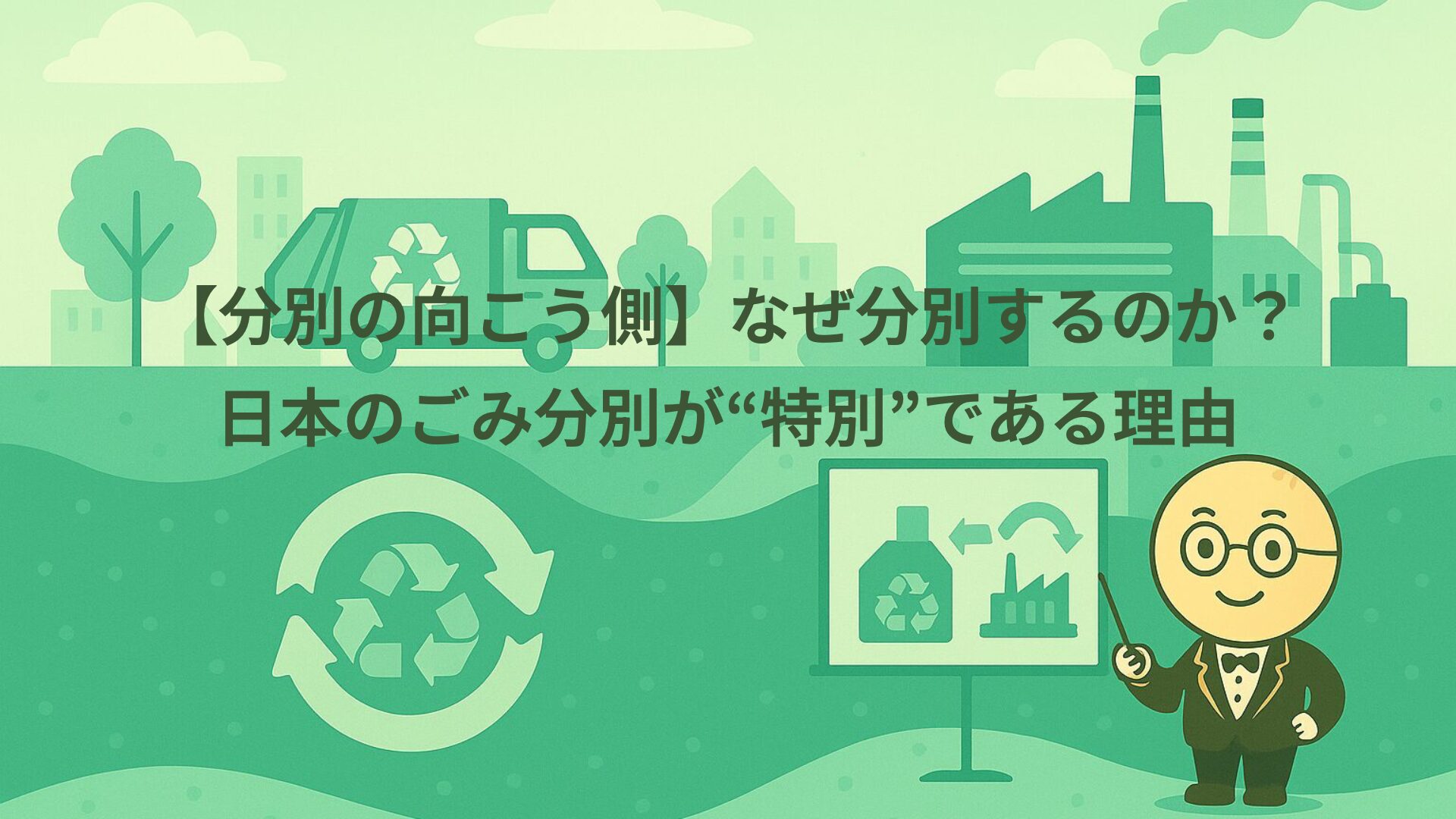【プラごみの向こう側】容器包装プラスチックのリサイクルと処理フロー

ヨーグルトカップ、食品トレイ、レジ袋――。
毎日のように目にするプラスチックごみの多くには、くるりと矢印の「プラマーク」が付いています。
これは容器包装プラスチック(容リプラ)のマークで、中身を包んだり守ったりするための袋や容器で、家庭ごみの中でも特に排出量が多いグループです。
しかし、収集車に載せた瞬間から、その行方は私たちの目から見えなくなります。
いったいどんな工程をたどり、最終的にどこへ向かうのか?
この記事では、容リプラの制度の背景から処理フロー、リサイクル製品として暮らしに戻ってくるまでを、現場の流れに沿って丁寧にたどります。
容器包装プラスチックとは?
プラマークの意味は?
容器包装プラスチックとは中身を使い終えた「容器」や「包装」で、材質がプラスチックのものを指します。
ここで重要な目印となるのが 「プラマーク」 です。
プラマークが付いている=容器包装かつプラスチックであることを意味します。
- 食品トレイ
- カップ麺容器
- ポリ袋
- ラップ
- 発泡スチロール緩衝材
- 菓子袋
- ボトルのキャップ・ラベル(※ボトル本体は「ペットボトル資源」)
ここで大切なのは、「モノ」そのものと「モノを包むもの」の違いです。
- プラの対象になるもの:「包材」
- 商品を包む袋や容器、配送時の緩衝材など。
- プラの対象外:「製品」
- ハンガー、バケツ、スプーンなど、プラスチック製でもそれ自体が商品であるもの。
つまり「同じプラスチックでも、役割で分けられる」という点が容器包装プラスチックの大きな特徴です。
この区別が「容器包装リサイクル法」の制度に結びついていくのです。

制度の背景 ― 容器包装リサイクル法
1995年に制定された「容器包装リサイクル法(容リ法)」は、容器や包装ごみのリサイクルを進めるための法律です。
背景には、当時増え続けていたプラスチックごみによる埋立処分場の逼迫問題がありました。
この制度によって:
- 消費者 → 容リプラを分別排出
- 自治体 → 分別収集・中間処理
- 事業者(メーカーなど) → リサイクル費用を負担
という役割分担が仕組み化されました。
自治体によってルールが違うのはなぜ?
ところで、容リプラの分別ルールは全国一律ではなく、自治体によって細かい違いがあります。
これは「気まぐれ」ではなく、実際には以下のような条件が関わっています。
- 受入先(再生工場)の仕様差:
- 工場によって受け入れられる素材や異物許容範囲が異なる。
- 設備差:
- 近赤外線選別機や洗浄ラインがあるかどうかで、扱える範囲が変わる。
- コスト構造:
- 選別や洗浄にかけられる費用と、再生材として売れる単価のバランスを考慮。
- 運用方針:
- 「燃料化で効率的に処理する」か「なるべくマテリアルリサイクルに回す」かの考え方が自治体で異なる。
さらに近年は、一部自治体で「資源プラスチック」として製品プラも含めた混合回収が始まっています。
出し方は簡単になる一方、異物や汚れの影響は大きくなるため、“きれいに出す”ことの重要性はむしろ高まっているのが現場の実感です。
自治体ごとに異なる現状が混乱を招いていると感じます。
全国統一ルールを作って運用されるようになれば良いと思うのですが、業界的になかなか難しいというのが実情のようです。
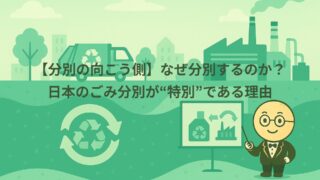

ゴミ箱の向こう側 ― 容リプラの行方は?
ここからは、家庭から出された容リプラがどのように資源化されるのかを見ていきましょう。
容リプラの処理フロー
イメージしやすいように、タイムライン形式で整理します。
- 地域ルールで分別された容リプラが中間処理施設へ。
- においや汚れ、異物混入を確認し、危険物(電池・ライター等)はここで除去。

- 袋を破ってほぐし、ベルトコンベヤ上で紙・金属・ガラスなどを除去。
- スクリーンで細かい異物もふるい落とす。

- 風力や近赤外線(NIR)でフィルムと成形品を分け、PP・PEなど素材ごとに分類。
- 自動機が苦手なものは人の手で補完。
- 素材ごとに圧縮してベール化。
- 施設によっては洗浄・粉砕してから出荷。
- 発泡スチロールは減容機でインゴットに。
- 粉砕・洗浄・比重分離を経て、乾燥後に溶融・押出してペレット化。
- ごみ袋・プランター・パレットなどの原料に。
- 多層フィルムや汚れの強いものは固形燃料化(RPF)や熱回収に。
- 残渣は埋立へ。

このように、容リプラの処理工程は「資源として使えるかどうか」を丁寧に見極めるステップの積み重ねです。
きれいに出されたプラほどマテリアルリサイクルに乗りやすく、汚れや異物が多いものほど燃料化・熱回収に回りがち。
家庭でのちょっとした心がけが、向こう側の処理フローを大きく左右しています。
暮らしに戻ってくるリサイクル製品と課題
容リプラは回収・再生を経て、さまざまな製品として再び私たちの生活に戻ってきます。
- ごみ袋・梱包フィルム(PE/PP再生材)
- 公共ベンチ・デッキ材・プランター
- 物流パレット・通い箱
- 発泡PS由来の文具・梱包材
ただし現在のリサイクルプラスチックは、主に「純度をあまり求められない製品」に使われることが多いのが実情です。
異素材や着色が混じっていても支障の少ない黒色パレットや屋外資材といった用途です。
一方で、食品容器や包装材など「高い純度が求められる分野」にもリサイクル材を広げていくことが期待されています。
その実現には、家庭から出す段階での異物除去や汚れを減らす分別の工夫が不可欠です。
「分ける」が「戻ってくる」につながるだけでなく、その“戻り方”の質を高めることにもつながります。
あなたのひと手間が、リサイクルの用途を広げる力になるのです。
有効活用のカギは“出すときのひと手間”
容リプラのリサイクル率を左右する最大のポイントは、実は家庭での出し方にあります。
- 汚れを軽くすすいで出す。
- 異素材(スプーン、金属キャップ等)を外す。
- 水分を切ってから袋に入れる。
このひと手間が、処理工程での歩留まりや最終的なリサイクル品の品質を大きく左右します。
「燃やした方が効率的?」という視点
効率面だけ見れば「最初から燃やしてエネルギー利用した方がいい」という議論もあります。
日本の焼却炉は高性能で、発電まで行える施設も多いからです。

確かに、エネルギー効率だけでいうとこの主張は正しい面もあることは事実です。
分別して集める手間とコスト、マテリアルリサイクルに要する手間とコストを短順位計算するとプラスチックを新たに生産した方が効率が良い場合はあります。
しかし、ここには資源としての視点が抜けていると私は思います。
いかに効率的に資源としてプラスチックを集めるか、リサイクルの可能性を残すためには、市民が分けて出すという協力が前提条件になります。
プラスチックが石油由来ということを考えると、限られた資源を採掘しワンウェイ的に消費するよりも社会の中で循環させたい。
そんな思いを実現するためのスタート地点が「捨てかた」なのです!
まとめ:資源に“戻す”か、エネルギーで“使い切る”か
容リプラの処理現場では、
- 素材として再び活かす(マテリアルリサイクル)
- 戻せない分は燃料や熱として活用する(エネルギー回収)
という二段構えで、最終的に埋立に回る量をできるだけ減らす取り組みが続けられています。
そして、その分かれ道の入口にあるのが 家庭での排出の仕方。
「軽くすすぐ」「異物を外す」「危険物を混ぜない」――この基本を守るだけで、資源として活かせる量と質は大きく変わります。
sutekatainfo.comでは、家庭で迷いがちな“捨てかた”を入口に、ルールや背景・意味を紐解き、納得感を持って行動できる情報をお届けしていきます。
関連リンク