【スマホ・タブレットの捨てかた】リサイクルプログラム活用のすすめ

現代社会では、スマホやタブレットなどの小型家電が私たちの生活に欠かせない存在となっています。
最近でこそケータイを2年ごとに買い換えるということも少なくなりましたが、1人が複数台所有していたりと、買い替え頻度は少なくありません。
機種変更後の昔のケータイが家に眠っているという方もいるのではないでしょうか。
本記事では、スマホやタブレットのリサイクル方法について詳しく解説し、環境に優しい選択をサポートします。
リサイクルプログラムがたくさん!ぜひ活用を
スマホやタブレットのリサイクルを促進するために、さまざまな企業や団体がリサイクルプログラムを提供しています。
どれでも良いので使いやすい方法で、適切なリサイクルをお願いします。
メーカーのリサイクルプログラム
Appleのリサイクルプログラム

スマホの王様iphoneを販売するAppleでは、使い終わったiPhoneやiPadをApple Storeや宅配で回収し、無料でリサイクルしています。
製品の下取りもその一環ですし、宅配での引き取りもやっています。
Appleのリサイクルプログラムを利用することで、古いデバイスが適切に処理され、新しい製品の製造に再利用されます。
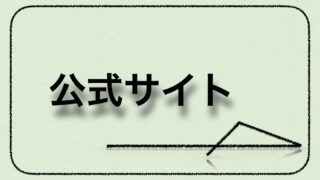
Googleの「リサイクルプログラム」

Googleも使い終わったPixelスマホやその他のデバイスを無料で回収し、リサイクルしています。
Googleのリサイクルプログラムでは、デバイスを郵送するだけで簡単にリサイクルが可能です。
また、リサイクルされたデバイスから得られた資源は、新しい製品の製造に再利用されます。
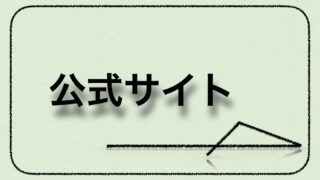
通信事業者のリサイクルプログラム

(https://www.tca.or.jp/mobile-recycle/)
ドコモやau、ソフトバンクなどの通信事業者もスマホやタブレットを店頭で回収する取り組みを行なっています。
携帯電話・PHSのリサイクル活動に取り組む「モバイル・リサイクル・ネットワーク(MRN)」のプログラムのもと、回収されたデバイスは分別・リサイクルされ新たな製品へと生まれ変わります。
近くにある店舗に持ち込むだけなので簡単でおすすめです。
- NTTドコモの「ケータイリサイクル」
-

出典:ドコモ(https://www.docomo.ne.jp/corporate/csr/ecology/resources/recycle/) NTTドコモは、使い終わったスマホやタブレットを店頭で回収し、リサイクルしています。
集められたスマホや携帯電話は分解・分別され、プラスチックは油化して燃料にされたり、金属類は精錬されて新しい製品へと生まれ変わります。
ドコモは環境省から広域認定の認可を受けているとのことで、あんしん・安全なリサイクル工程を確立しており、店頭に持ち込まれた携帯電話にその場で穴を開けて使えなくするといったところも安心です。
リサイクルに出した携帯電話がどのように処理されるのかを、動画で分かりやすく紹介されていますので、公式サイトを覗いてみてください。
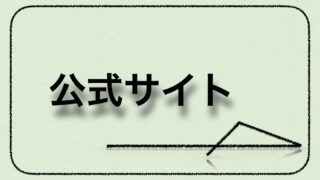 ドコモ ケータイリサイクル
ドコモ ケータイリサイクル
- ソフトバンクの「スマホリサイクル」
-
ソフトバンクも使い終わったスマホやタブレットを店頭で回収し、リサイクルしています。
さらに、ソフトバンクのリサイクルプログラムでは、回収されたデバイスの一部を修理して再利用する取り組みも行っています。
また、レアメタル採掘国の一つであるコンゴ民主共和国に対して、ケータイ電話のリサイクルと連動して寄付を行う取り組みも実施していました。
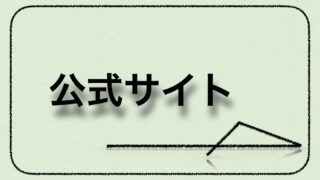 ソフトバンク ケータイリサイクルへの取り組み
ソフトバンク ケータイリサイクルへの取り組み
家電量販店のプログラム
ビックカメラやヨドバシカメラなどの家電量販店もリサイクルプログラムを提供しています。
これらの店舗では、使い終わったスマホやタブレットを回収ボックスに入れるだけで、簡単にリサイクルが可能です。
さらに、店舗によってはリサイクルに協力することでポイントが貯まる特典もあります。
地方自治体のプログラム
多くの地方自治体も、小型家電のリサイクルプログラムを実施しています。
自治体のリサイクルセンターや指定の回収ボックスにデバイスを持ち込むことで、無料でリサイクルが可能です。
自治体のウェブサイトで、最寄りの回収場所や回収方法を確認することができます。
回収・買取サービスの活用
忙しくて回収ボックスに持ち込み無暇がない、一度に持っていくには量が多いという方は、宅配で完結できる回収サービスを活用するのも良い選択です。
スマホの宅配リサイクルサービスなら、自宅から手軽にリサイクルができます。
宅配便で回収 → 国認定工場にて適切にリサイクル
国からも認定を受け、各自治体とも連携をして回収・リサイクルをしているので安心!
箱に入れば、パソコン・小型家電何点詰めても1箱分の料金でお得です

簡単3ステップでスマホをリサイクル
- 申込
- サービスのウェブサイトから宅配リサイクルをお申し込み
- 必要な情報を入力するだけで、回収キットが自宅に届きます
- 梱包と発送
- 届いた回収キットに、リサイクルしたいスマホを梱包。
- その後、指定の配送業者に集荷を依頼するだけでOK。
- リサイクル処理
- 回収されたスマホは専門のリサイクル施設で適切に処理され、貴重な資源が再利用されます。
便利で安心
- 自宅で完結
- すべてのプロセスを自宅から完了できます。
- 店舗に持ち込む手間が省けます。
- 個人情報の保護
- スマホのデータは安全に処理され個人情報の流出を防ぎます。
- 環境に優しい
- リサイクルされたスマホから得られた資源は新しい製品の製造に利用
- 資源の有効活用と環境保護に貢献
Amazonや楽天といったECサイト経由でもリネットの家電リサイクルを注文して利用することができます。
ぜひ、この便利な宅配リサイクルサービスを利用して、スマホのリサイクルにご協力ください!
スマホやタブレットは資源!
スマホやタブレットなどの小型家電には、金や銀、レアメタルなどの貴重な資源が含まれており、適切にリサイクルすることで再利用が可能です。
くれぐれも、燃えるゴミと一緒にゴミ箱にポイということがないようにしてください。
また、不適切な処分は環境を害するだけでなく、燃えるゴミからの発火など事故を招く恐れもあります。


資源の有効活用
1台のスマホには、約0.02グラムの金、0.36グラムの銀、そして少量のレアメタル(インジウム、タンタル、パラジウムなど)が含まれているそうです。
皆さんも都市鉱山という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、製品として市場に出回っているレアメタルの総量は、1年で採掘される量の数倍以上だそうです。
これらの資源を適切にリサイクルして活用できれば、新たに採掘する量を減らせ環境負荷も低減できます。
環境保護
小型家電の不適切な廃棄は、焼却された際の有毒ガスや環境流出した場合の土壌や水質の汚染を引き起こす可能性があります。
特に、バッテリーに含まれる有害物質は環境に大きな影響を与えることがあります。
リサイクルを通じて、これらの有害物質を適切に処理し環境への負荷を軽減することが重要です。
廃棄物の削減
リサイクルを行うことで単純に廃棄物の量を減らすことができます。
ゴミとして償却されたり埋め立てられる量を減らし廃棄物処理にかかるコストも削減できます。
さらに、リサイクルされた材料は新しい製品の製造に利用されるため循環型社会の実現に貢献します。
コスト的メリット
リサイクルされたスマホから得られる資源は、新たに採掘するよりもコストが低くエネルギー消費も少ないという説もあります。
例えば、金を新たに採掘する場合、1トンの鉱石から約1グラムの金しか得られませんが、リサイクルでは1トンの使用済みスマホから約300グラムの金を回収できます。
これにより、採掘に伴う環境破壊やエネルギー消費を大幅に削減できます。
リサイクルの手順:安全にリサイクルするために
スマホやタブレットをリサイクルする際には、いくつかの重要な手順を踏む必要があります。
以下に、リサイクルの基本的な手順を紹介します。
1. データの消去
リサイクル前に、個人情報を含むデータを完全に消去することが重要です。以下の手順でデータを消去しましょう。
- バックアップの作成
- 重要なデータは事前にバックアップを
- クラウドサービスや外部ストレージを利用すると便利です。
- 工場出荷状態にリセット
- デバイスの設定メニューから「工場出荷状態にリセット」を選択しデータを完全に消去
- 個人情報が第三者に漏れるリスクを防ぎます。
2. 回収ボックスの利用
認定事業者の回収ボックスを利用することで、安全かつ確実にリサイクルが行えます
以下の手順で回収ボックスを利用しましょう。
- 回収ボックスの場所を確認
- 各事業者のウェブサイトや自治体の情報を確認し、最寄りの回収ボックスの場所を調べます。
- デバイスの持ち込み
- デバイスを回収ボックスに持ち込み、指定の方法で投入します。
- 多くの回収ボックスは簡単にデバイスを投入できるよう設計されています。
3. リサイクルの追跡
リサイクルされたデバイスがどのように処理されるかを追跡することも可能です。これにより、リサイクルの透明性が確保されます。
- 追跡サービスの利用
- 一部のリサイクルプログラムでは、デバイスのリサイクル状況をオンラインで追跡できるサービスを提供しています。
スマホのリサイクルの流れと注意点
スマホやタブレットのリサイクルフロー
スマホやタブレットなどの小型家電をリサイクルプログラムに出した後、どのように処理されるのかを知ることで、リサイクルの重要性を実感できます。
小型家電リサイクル法
日本では、2013年に施行された「小型家電リサイクル法」に基づき、小型家電のリサイクルが推進されています。
この法律は、使用済みの小型家電から有用な資源を回収し、再利用することを目的としており自治体や認定事業者が回収・リサイクルを行うことになっています。

法律と認定事業者
スマホやタブレットなどの小型家電のリサイクルは、法律に基づいて適切に行われなければいけません。
違法業者に渡ったスマホが有価金属だけを取り除いて残りは不法投棄されていたといった事例もあるようですので、適切な知識のもとリサイクルに取り組みたいところです。
認定事業者の役割

認定事業者は、小型家電リサイクル法に基づいて、適切にリサイクルを行うための認定を受けた企業や団体です。
これらの事業者は、回収された小型家電を分別・処理し、資源を再利用するためのプロセスを管理しています。
認定事業者の回収ボックスや車両には認定マークが付いており、消費者はこれを確認して利用することができます。
消費者の協力の重要性
小型家電炉リサイクルは、行政やメーカの取り組み・仕組みだけではうまくいきません。
なぜなら、集まらないから。
消費者一人ひとりの協力が持続可能な社会の実現に大きく貢献します。
ぜひ、身近なリサイクルプログラムを利用して、スマホやタブレットのリサイクルに参加しましょう。
まとめ
リサイクルは、私たち一人ひとりができる環境保護の重要なアクションです。
スマホやタブレットなどの小型家電を適切にリサイクルし、持続可能な社会の実現に貢献しましょう。
sutekatainfo.comでは、今後もさまざまなリサイクルプログラムや環境保護の取り組みを紹介していきますので、ぜひご覧ください。

関連記事






sutekatainfo.comでは、家庭で迷いがちな“捨てかた”を入口に、ルールや背景・意味を紐解き、納得感を持って行動できる情報をお届けしていきます。
sutekatainfo.comでは、家庭で迷いがちな“捨てかた”を入口に、ルールや背景・意味を紐解き、納得感を持って行動できる情報をお届けしていきます。


