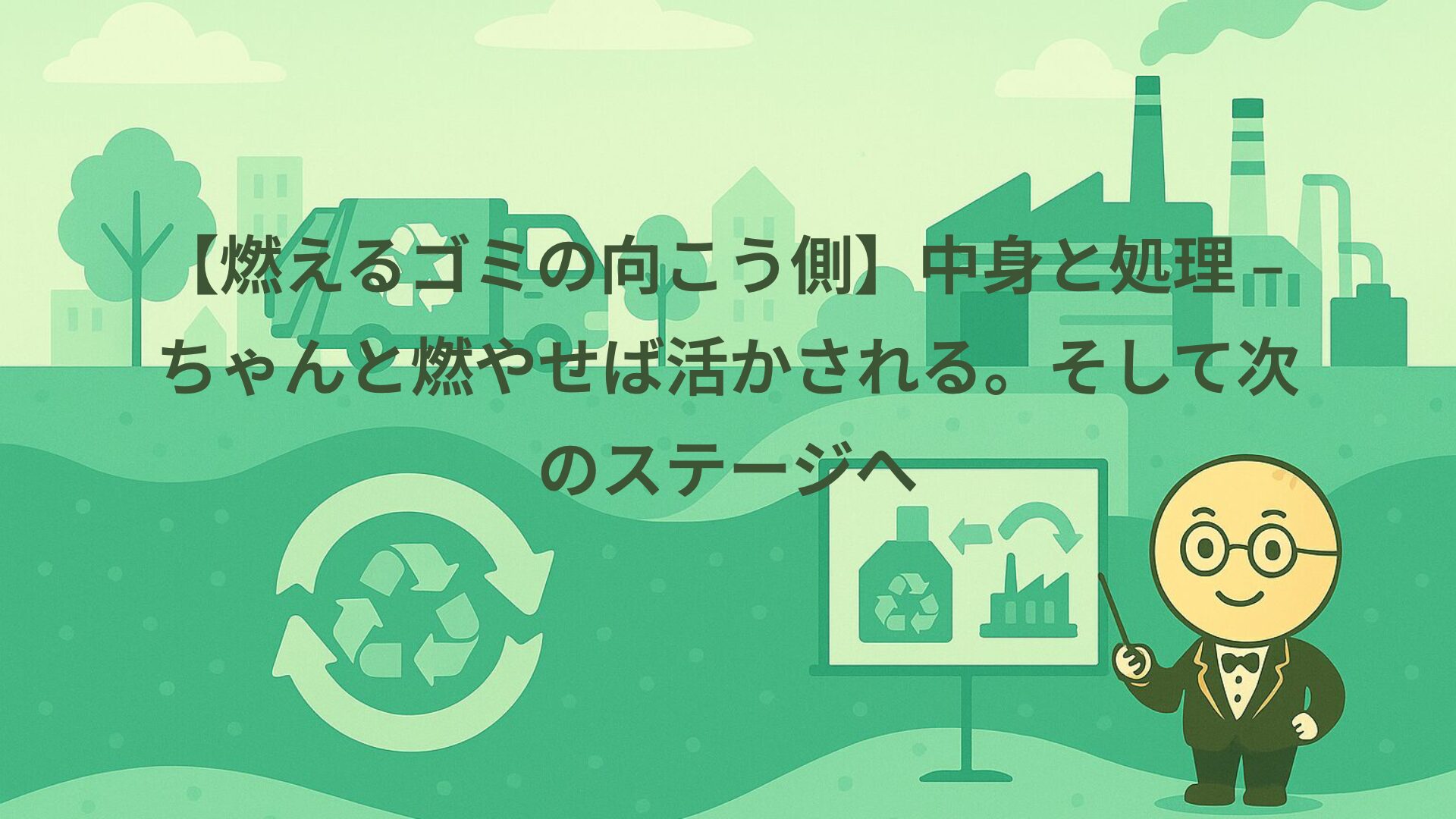【焼却施設の向こう側】燃えるゴミは“エネルギー”に!!

見えなくなったあと、何が起きている?
家庭ごみは収集車に載った瞬間、衛生と減容を最優先に処理へ進みます。
そして多くの施設ではここにエネルギー回収(電気・熱)が加わります。
この記事では、生活者目線で“焼却処理の全体像が見える”という基礎をおさらいする内容です。
“燃やして終わり”ではありません。
燃やし方の制御/エネルギーの取り出し/大気・残さの管理が揃って初めて、焼却は街の衛生を支える仕組みになります。
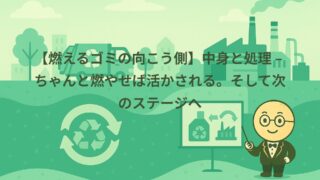
焼却処理の全体像
焼却施設の役割:暮らしに直結する“3本柱”
家庭ごみの処理は「何のためにするのか」で見ると3点に集約されます。
まず衛生と減容を確実に──そのうえで、条件が整う施設ではエネルギー回収。
この順番で押さえると全体像がぶれません。
- 衛生
- 悪臭・害虫・病原体の抑制。収集頻度を支え、街の衛生を守る。
- 減容
- 体積と重量を大幅に減らし、運搬・最終処分の負担を軽減。
- エネルギー回収(可能な範囲で)
- 電気・熱として地域還元(プール・庁舎・館内利用など)。
全体像:5つの工程で見る「ごみの行方」
まず先に全体の流れをつかむと、各パートの役割が理解しやすくなります。
ピットで混ぜて均し、発熱量と水分を平準化。
高温・安定燃焼で衛生的に減容。
蒸気→発電/熱供給に活用。
中和・ろ過・吸着・脱硝で空気を守る。
金属回収+安定化で、最終処分量を最小に。
とてもシンプルにまとめると5ステップに分けられます。
「衛生・減容をまず確実に」、可能なら「熱・電気も地域で活用」という順番で設計が選ばれます。
焼却方式の違い
実は焼却炉の形式にもいくつか種類があります。
少々マニアックですが、基本的な違いをざっくり押さえておきましょう。
- ストーカ式(移動火格子)
- 幅広いごみ性状に対応。日本の標準方式。
- 流動床式
- 細粒・均一なごみに適し、反応が速い。
- ガス化溶融等
- スラグ化など自治体方針で採用される派生方式。
方式は地域ごとの条件や考え方(ごみ質・規模・立地・熱の使い道、灰の扱い、維持管理体制)で最適解が変わります。
どれも一長一短あり適材適所で定められています。
焼却処理の流れを解説
工程① 受入〜前処理:燃やしやすい“燃料”に整える
収集車からピットと呼ばれる大きな貯留槽へ。
ここは単なる置き場ではなく、後工程の安定運転を左右するブレンダー(混合槽)の役割を持ちます。
- 混ぜて均す(ブレンディング)
- 日によってばらつく水分・発熱量・粒度をクレーンで攪拌。
- 均質になるほど、後段の燃焼・蒸気のムラが小さくなります。
- 臭気は負圧で館内へ
- 建屋はわずかな負圧に保たれ、臭気は外へ漏れにくく、炉の燃焼空気として取り込まれます。
- 危険物チェック
- 電池・スプレー缶・長尺金属などは運転トラブルや発火の原因。
- 投入前後で目視・抜き取り確認を行う場合もあります。
ピットでの“ひと手間”=味を均一にする下ごしらえです。
ここが整うと、燃焼も発電も安定してよく回るようになります
工程② 燃焼(焼却):高温・安定・完全燃焼
ごみは投入→乾燥→熱分解→燃焼→焼成の順で処理されます。
ポイントは時間・温度・混合を外さないことです。
- 空気・温度の自動制御
- 一次/二次空気と炉内温度、O₂・COなどの指標を見て燃え方を調整。
- 空気が少なすぎても多すぎてもロスになります。
- 完全燃焼の意味
- 煙や臭いを抑え、ダイオキシンの発生も防ぎます。
- 高温域で適切に燃やし、未燃を残さないのが基本。
- 残さは主灰へ
- 燃え残りを灰として次工程に送ります。
生ごみの水切りは家庭でできる“燃料改質”。
余計な水は熱を奪い、燃焼を不安定にします。
工程③ エネルギー回収:蒸気→電気・熱
一定規模以上の施設では、炉の熱で廃熱ボイラを温めて蒸気を作り、発電や熱供給に使います。
電気だけより熱も活かす(熱電併給=CHP)方が、地域全体の総合効率は高くなります。
- 蒸気条件とトレードオフ
- 高い圧力・温度は発電に有利。
- ただし材料の耐食・防食や運転コストとのバランスを取ります。
- 使い道で価値が変わる
- 電力として売る/施設内の空調・給湯に使う/近隣のプール・庁舎・温浴施設へ熱供給するなど、地域事情で最適解が決まります。
- 館内利用のみのケース
- 外部供給はなくても、館内で熱や空気の予熱に回すのが一般的です。
同じ“1トンのごみ”でも、熱の使い方で価値が上がります。
設計は需要(熱の使い道)から逆算されます。
工程④ 排ガス処理:空気を守る多段対策
燃やす以上、汚さない仕組みが不可欠です。
化学反応とろ過・吸着を重ね、煙突前で連続監視します。
要点は高温燃焼→急冷→捕集の組み合わせ。
- 酸性ガス(HCl・SOx):
- 消石灰などで中和。
- ばいじん:
- バグフィルタでろ過捕集。
- ダイオキシン・水銀等
- 活性炭で吸着。
- NOx
- SNCR/SCRで還元。
しっかりと排ガス処理されるので現在稼働中の償却施設からは有害ガスはほとんど出ません。
煙突から白く見えるのは水蒸気のことが多く、排ガスの温度や外気条件で見え方が変わります。
工程⑤ 灰処理:資源回収と安定化
燃焼後も仕事は続きます。資源を回収し、残る部分は環境的に安定な形へ。
- 主灰(ボトムアッシュ):
- 磁選や渦電流分離で鉄・アルミを回収。
- 自治体によっては基準を満たした材料を路盤材等に活用。
- 飛灰(フライアッシュ):
- 重金属等を含む微細灰は、薬剤で不溶化(固化・安定化)し、管理型処分場へ適正に処分。
- ねらい
- 資源回収の最大化×最終処分量の最小化。
- 処理条件の最適化は回収率と処分コストの両方に効きます。
もう一歩の視点
家庭の“ひと工夫”がエネルギーに変わる
仕組みがわかったら、「ゴミを出すときにできること」をエネルギーの視点で見直してみましょう。
むずかしいことは不要、燃えやすく・混ざりにくく・安全の3点です。
- 生ごみは水を切る
- 袋の口を開けたまましばらく置く、新聞紙や水切り袋で余分な水を吸わせる。
- → 乾燥に奪われる熱を減らし、蒸気の安定に貢献。
- 電池・バッテリーは専用回収へ(内蔵型も含む)
- → ピットや搬送の発火・停止を防ぎ、連続運転を守る=結果として安定したエネルギー回収に直結。
- スプレー缶は“使い切って”から指定ルート
- → 残圧による破裂・着火を防ぐ。混合や燃焼の乱れを抑えます。
- プラはまず資源ルートへ(容リ/製品プラのルールに沿って)
- → 資源化が原則。
- 収集日・ルールを守る
→ ピットでの混合が効きやすくなり、季節や日によるごみ質のムラを緩和。
興味が湧いたら、施設見学へ
実は、清掃工場(ごみ焼却施設)は見学にオープンなところが多く、無料・予約制で気軽に行けます。
展示室や見学デッキからピットやクレーンの動き、ボイラやタービンの窓越し見学など、教科書よりずっと分かりやすい体験ができます。
- 自治体サイトで「清掃工場 見学」を検索→予約ページへ。
- 開館日・所要時間(45〜90分めやす)と対象年齢を確認。
- 写真撮影の可否・安全案内(ヘルメット等の貸与)に目を通す。
合わせてこれらもチェックしておくと安心です。
小学校の社会科見学、覚えていますか?親子での再訪もおすすめです。
実物を見ると、家での分別の話がぐっとしやすくなります。
まとめ:今日から“説明できる”
焼却施設はまず街の衛生を守り、ごみを小さくする装置です。
そのうえで条件が整う地域では、炉の熱を蒸気に変えて電気や温水として活かします。仕組み自体は受入→燃焼→(エネルギー)→排ガス→灰の5工程とシンプルですが、設計は地域事情しだい——すべてが発電や外部熱供給を担うわけではありません。
家庭では「水切り・使い切り・分ける」を心がけるだけで、燃えやすさと安全が上がり、回収されるエネルギーの質もよくなります。
もっと知りたくなったら、オープンな清掃工場の見学がいちばんの近道です。
sutekatainfo.comでは、家庭で迷いがちな“捨てかた”を入口に、ルールや背景・意味を紐解き、納得感を持って行動できる情報をお届けしていきます。
関連リンク