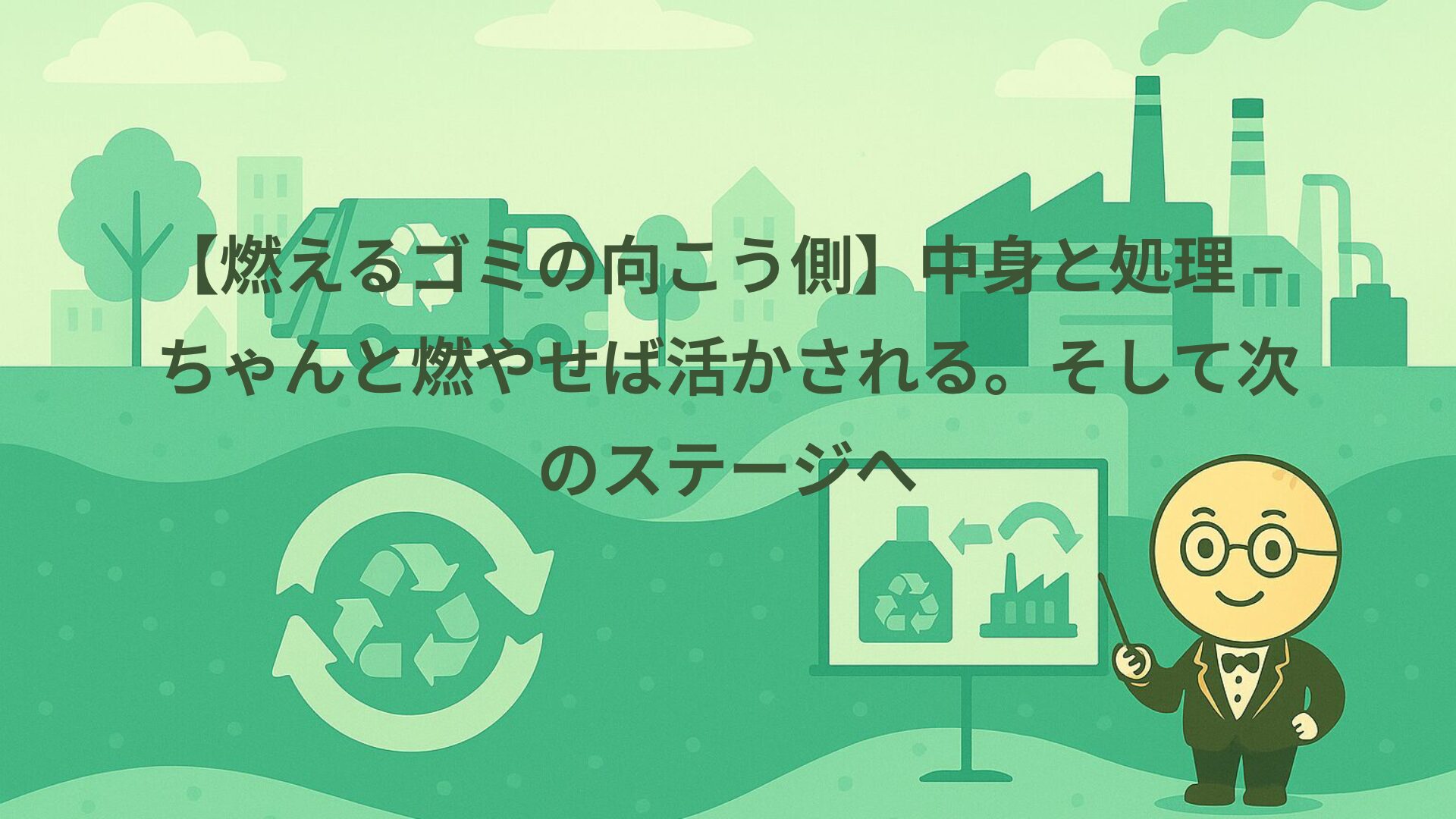【ごみ収集の向こう側】収集の仕組みと各家庭ができること

家の前からごみが消えるまでの数時間。
そのあいだにも、働く人とごみ処理の仕組みが、見えないところで動いています。
最初に全体像をつかんでから、キホン → しくみ → どれくらい積める → 何が積めない → 行き先 → におい対策 → 出し方の順で、読みやすく解説していきます。
流れがわかると、「なぜそのルールなのか」が腹落ちしますよ。
ごみ収集のキホン(まずはここから)
まずは基本から整理します。
毎日のゴミの回収は「誰が担い」「どこから集め」「いつ・何を運ぶか」という3点で成り立っています。
ここを押さえると、時間厳守や分別の“理由”が見えてきます。
- だれが?
- 原則市区町村。
- 直営または民間委託。
- どこから?
- 多くは集積所。
- 地域によっては戸別収集や集合住宅のダストボックス。
- いつ・なにを?
- 可燃・不燃・資源・粗大など区分別に曜日・時間が決定。
- 時間厳守が安全と効率に直結します。
収集車のしくみ(どう積んで、どう運ぶ?)
街で見かけるパッカー車(塵芥車)は、後部ホッパに入れたごみを油圧の圧縮板で荷箱へ押し込み、積載効率を高める専用車です。
停車→積込→圧縮→離脱を数十秒で繰り返すため、機構と安全装備が“作業の速さと安全”を同時に支えています。
- 基本構造
- ホッパ → 圧縮板 → 荷箱(タンク)
- 安全装備
- 回転灯・警報・バックカメラ。後退は一旦停止が原則。
- 汚水処理
- 荷箱のドレンで排水(=生ごみの水切りが効く理由)。
- 品目に応じた車両
- 資源回収車(混ざらない運搬)、平ボディ/クレーン付(粗大対応)など。


なんでも積めるの?(積めないもの・要注意品)
結論はNOです。
収集車は“家庭ごみを安全に”運ぶ車です。
危険物や法令で別ルートの品は積めません。
迷ったら自治体の分別表を確認し、電池・バッテリーは必ず専用回収へ。
- 危険・発火性
- 充電式電池(リチウム)、モバイルバッテリー、ボタン電池、未使い切りスプレー缶・カセットボンベ、花火・ライター
- 法令で別ルート
- テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン(家電リサイクル法)、パソコン(PCリサイクル)、バイク・タイヤ・消火器・ガスボンベなど
- 鋭利・重量物
- 包まず出すガラス・刃物、極端に重い袋(作業員の負担・機器故障の原因)

どのくらい積めるの?(容量のめやすと満車のなり方)
収集車の“満車”は2通りです。体積(荷箱)が先に埋まる場合と、重量(法定積載)が先に限界に達する場合です。
地域の道路事情や品目で車型は変わりますが、まずは代表的な容量の目安を押さえましょう。
- 小型:2t車クラス(狭い路地向け/ボディ目安 2〜3 m³)
- 中型:3〜4t車クラス(標準的な市街地/6〜8 m³)
- 大型:7〜8t車クラス(幹線・直行搬入向け/9〜12 m³)
同じ体積でも、水分が多い可燃ごみは重さ先行、かさがある資源ごみは体積先行で満車になります。
満車になれば処理場へ搬入→また町へ。地域によっては午前と午後で同じ車が何往復もします。
重量いっぱいになると搬入回数が増えます。
生ごみの水切りは、におい対策だけでなく重量を落として往復を減らすための具体策でもあります。
集めたごみはどこへ行く?(処理場へ直行、必要に応じて何往復も)
家庭・集積所 → 収集車 → 処理場(計量→荷下ろし→車両洗浄) → 必要に応じて再び町へ。
この往復サイクルで、午前・午後と何度か回転数を稼ぐのが一般的です。
それぞれ焼却施設や選別施設などへ搬入されます。
- 可燃ごみ
- 清掃工場のピットへ → 焼却 → 発電・熱利用 → 灰の処理へ。
- 資源ごみ
- 選別施設で素材別に分け直し → 圧縮・ベール化 → 製紙・製鉄・樹脂再生へ。
- 不燃・粗大
- 破砕・手選別で金属等を回収 → 残ったものは埋立へ。


においが嫌…を前向きに(街の衛生 × エネルギー)
ゴミ収集車を見かけると、「においがちょっと、、」と思う方もいるでしょう。
しかし、収集車は街の衛生を守るしくみであると同時に、排出者側が工夫できる点もあるのです。
- 素早い回収=衛生のコア
- 腐敗や害虫の餌を短時間で断つことで、街の清潔を保つ。
- 設備側の対策
- 車は密閉荷箱+ドレンで漏れを抑制、処理場は負圧換気・脱臭で拡散を防止。
- 私たちの一手でさらに減る:
- 生ごみは水切り、可能なら当朝に出す
- 二重袋+しっかり結ぶ
- 家庭によっては短時間の冷凍で臭源を封じる工夫も(無理のない範囲で)
可燃ごみの多くは電気や熱に変わります(プールや施設の温水に使われる地域も)。
水切りというにおい対策は、エネルギーの質を上げることにも繋がります。
今日からできる“出し方”のポイント(ブックマーク推奨)
ゴミ収集の仕組みは私たち一人ひとりが運行の一員であり、ごみ出しの瞬間から始まっています。
ルールの細部は地域で違っても、安全・におい・回収効率に直結する“共通パターン”です。
作業員のケガと車両トラブルを減らし、搬入の往復も抑えられます。出す前の30秒チェックとして、現場=家の前で考えてみて下さい。
- 時間・場所・区分を守る(往復サイクルを乱さない)
- 指定(透明)袋で、口をしっかり結ぶ
- 生ごみは水切り
- 電池・バッテリーは別回収へ
- スプレー缶・ボンベは使い切り(穴あけ可否は自治体ルール/火気厳禁)
- 刃物・ガラスは包んで「キケン」表示
- 中身入りを混ぜない(缶・びん・ペットは空+軽くすすぐ)
「重い袋1つ」より「軽い袋2つ」の方が良いそうです
安全・効率・故障防止の三方よしのためのひと工夫です。
まとめ——“少し丁寧に出す”が、最短で効く
収集車は体積と重量のルールで安全に積み、処理場へ運び、必要に応じて何往復も走ります。
においが気になるのは自然な感覚。でも、早期回収=街の衛生であり、エネルギー化というリターンもあります。
その後の処理のことも考えて少し丁寧に出す——それだけで、事故と遅延を減らし街の衛生環境を支えられます。
sutekatainfo.comでは、家庭で迷いがちな“捨てかた”を入口に、ルールや背景・意味を紐解き、納得感を持って行動できる情報をお届けしていきます。
関連記事