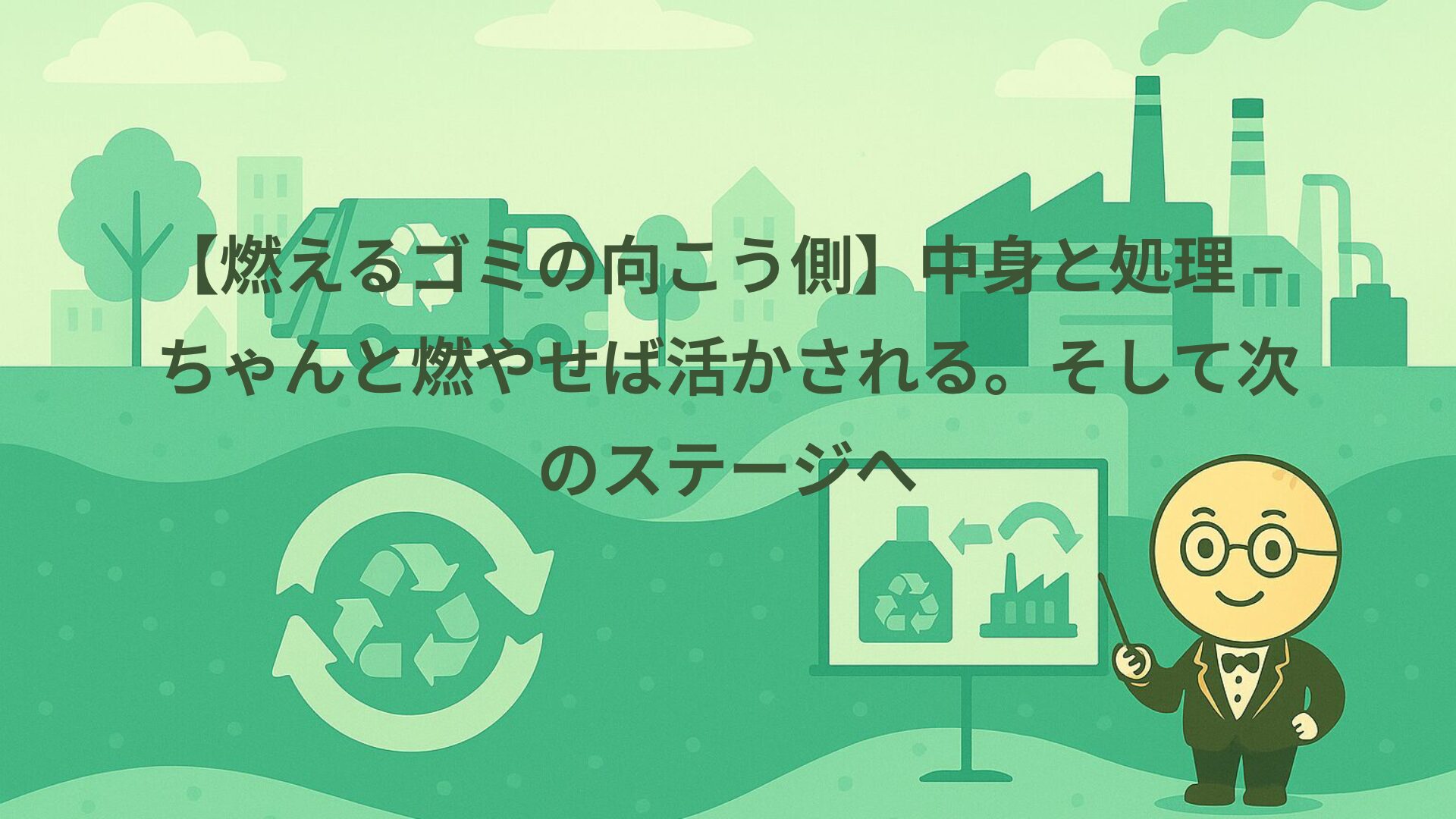【資源ごみ選別の向こう側】手選別×機械選別―売れる資源に戻るまで

プラごみなどの資源ごみは収集車に載った瞬間、私たちの視界から消えます。
運ばれる先は資源選別センター(MRF:Materials Recovery Facility)などの中間処理施設。
ここで「売れる資源」に仕立て直すための前処理=選別が行われます。
この記事では、現場の基本工程と“歩留まり”を左右する要因を、暮らしの視点で整理します。
「選別」の定義と位置づけ
日本の選別施設は「資源選別センター」「資源化選別施設」などと呼ばれ、役割はシンプルです。
- 家庭
- 分別して排出する
- 自治体
- 分別収集し、選別・保管(ベール化)までを担う
- 再商品化事業者・製鉄所・製紙工場など
- 受け取った資源を原料へ戻す(再商品化)
容器包装リサイクルの基本スキームでは、この「真ん中」を自治体が受け持ちます。
一方で新しい制度設計により、地域事情に応じて役割分担の幅が広がってきました(詳しくは後述)。
MRFは「回収物を市場で通用する品質に整える場所」というこのイメージがあると、以降の工程がすっきり入ってきます。
では、実際のライン上では何が起きているのかを順に見ていきます。
処理の流れ——“混ざり”をほぐして、資源だけを分ける
工程名や配置は施設によって異なりますが、代表的なフローは次のとおりです。
処理の順番は「ほどく→拾う→見分ける→仕上げる→束ねる」
受入検査 → 破袋・解砕 → トロンメル(回転ふるい)や各種スクリーンで粒度分級 → 風力選別で軽いもの/重いものを分け、コンベヤ上へ。
まずは“ほぐす・分ける”が要点です。
磁選機でスチール缶等の鉄を吸着回収 → 渦電流選別でアルミなど非鉄金属をはじき分け。
ここで金属系の回収率と純度が決まります。
近赤外線センサー(NIR)やカメラで材質・色を識別し、エアジェットで狙い撃ち。
PET/PE/PPの分けや、黒色・多層材の対応など、機械の“目”が主戦力です。
機械で取り切れない異物・汚れ・袋詰まりを人の目と手で補正。
ここで品質基準に合わせて“仕上げ”を行います。
材質ごとに圧縮梱包(ベール化)→ 品質検査 → 再生業者・製紙工場・製鉄所などへ出荷。
ここまでがMRFの仕事というのが基本形です。
最近は特に、プラスチックの分別が盛んです。
AIを使って素材判別するなど、ハイテク化も進んでいます。


現場の実態と“歩留まり”を落とすもの
理屈で見ればシンプルでも、現場はいつも“混入”とのせめぎ合いです。
設備は万能ではなく、季節や地域によって混ざり方も変わります。
だからこそ、どんな要因が歩留まりを下げるのかを知っておくと、家庭側の工夫がどこに効くのかが見えてきます。
- 汚れ・液残り
- 食品残渣や油分は、光学センサーの誤検知やベルト汚染→ライン停止清掃の原因に。
- 軟包材の絡み
- ラップ・フィルムなど細長いものはスクリーンやローラに絡み、ダウンタイムを招きます。
- 黒色・多層・全面シュリンク
- 識別難易度が上がり、取りこぼしや残渣率の上昇に。
- 危険物混入
- リチウム電池やスプレー缶は火災・爆発のリスク。
- 1回の事故で長時間停止と設備損傷に直結。
- 季節変動・地域差
- 行事・季節で組成が変わり、設定の微調整が必要になるケースも。

暮らしへの落とし込み——家でできる“3つだけ”
ここまでが工場側の努力ですが、私たちの暮らしの側からもできることがあります。
答えは、特別な道具でも最新技術でもなく、毎日のごく小さな所作にあります。
次の3つだけを押さえると、選別の質が目に見えて変わります。
- 使い切る・軽くすすぐ・水を切る
- センサーの視界がクリアになり、誤検知と清掃頻度が下がります。
- ラベル・キャップを外す
- 異素材混入率が下がり、ベール品質(売却単価)が安定します。
- 電池・ライター・刃物は別回収へ
- 安全確保は最大の資源化。事故ゼロが最大の“効率化”です。
「つぶす/つぶさない」「金属小物の扱い」などは自治体ルールが最優先。
迷ったら“混ぜない”のが基本です。
背景と構造——なぜ自治体で違う?誰がどこまでやる?
「うちの自治体はつぶす/つぶさないの指示が違うのはなぜ?」——そんな疑問の背景には、設備の有無、輸送距離、費用の積み上げ方といった“事情”があります。
制度の骨格を押さえると、地域差の意味合いが理解しやすくなります。
- 制度の骨格
- 容器包装リサイクルでは、自治体が**選別・保管(ベール化)**まで、再商品化は事業者が担うのが標準。
- 地域最適の幅
- 設備保有状況、輸送距離、処理費の積算方法、組成の違いによって、どの材をどこまで分けるかが変わります。
- 新プラ法以降
- 自治体が自ら再商品化計画を持つケースや、製品プラスチックの回収を取り込む動きも。結果として選別の深さ・ルールに地域差が生じます。
「混ぜて安く」ではなく、“売れる品質に整えるコスト”と“売れる価格”のバランス。
ここを外さない設計が、持続可能性を左右します。
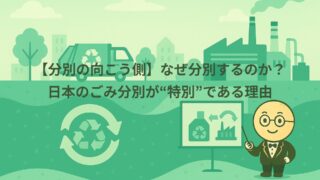
まとめ——“素材に戻す前の整え”が循環を決める
冒頭で“視界から消える先”と書きましたが、その見えない場所での仕事を想像できると、分別の意味は“面倒”から“合理”へと姿を変えます。
MRFは、資源ごみを市場で通用する“素材”に整える現場です。
機械選別の高度化が進んでも、家庭の質(清潔・適正分類)がベルト上の風景を変え、歩留まりと安全性を底上げします。
家の5秒=現場の1歩。それが資源循環のいちばんの近道です。
sutekatainfo.comでは、家庭で迷いがちな“捨てかた”を入口に、ルールや背景・意味を紐解き、納得感を持って行動できる情報をお届けしていきます。
関連記事